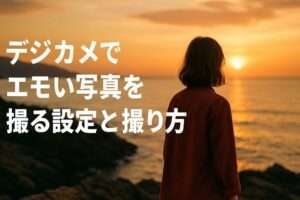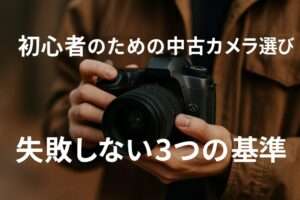カメラを買いに行った日のことを、いまでも覚えています。
ヨドバシのカメラコーナー。
前に立ちはだかる“黒い金属の壁”――一眼レフとミラーレス。
店員さんが「こちらは光学ファインダー搭載の一眼レフでして〜」と話し出した瞬間、私の頭の中には
「ファインダーって誰?」という声が響きました。
正直、最初の印象はこうです。
「どっちもカメラじゃん。」
しかしある日、ふと気づいたんです。
のぞいたときに見ているのは「現実」か「映像」か。
この一点で、両者はまったく別の生き物でした。
一眼レフは“鏡のあるカメラ”。
レンズから入った光を鏡とプリズムで跳ね返し、ファインダーまで運ぶ。
だから見えているのは「この瞬間のリアルな光景」。
そのかわり、シャッターを切る瞬間に「カシャッ」と鏡が跳ね上がる。
この“カシャッ”が、まるで舞台の幕が上がる音のようで、撮影者のテンションを上げるんです。
一方、ミラーレスは“鏡のないカメラ”。
光を電子信号に変えてモニターやEVFに表示します。
つまり「現実を、ちょっと未来っぽく見せてくれる」タイプ。
露出や色味、ピントのズレをリアルタイムで反映してくれるので、「失敗を事前に教えてくれる頼れる友」みたいな存在です。
違いをひとことで言えば、
一眼レフは“生の光で撮るロックバンド”、
ミラーレスは“電子の音で鳴らすシンセサイザー”。
どちらも音楽だけれど、ライブ感と便利さのバランスが違う。
この記事では、この「鏡あり・鏡なし」という根本の違いから、
AF性能、連写、手ぶれ補正、そして2025年の市場動向までを、
難しい専門用語を抜きにして、できるだけ“体験の言葉”で整理していきます。
この記事でわかること
・“鏡あり(=一眼レフ)”と“鏡なし(=ミラーレス)”の本質的な違い
・AF、連写、手ぶれ補正など、実際に使うとわかる体感の差
・子どもの行事、旅行、動画撮影など、用途別の選び方
・2025年の最新市場動向を踏まえた「後悔しない一台」選び
※この記事はインターネットという広い海を泳いで拾い集めた話をもとにしています。
波の高さも潮の向きも人それぞれ。
「そんな見方もあるのね」と笑って読んでいただけたら、それで十分です。
世の中は、ひとつの真実よりも、いろんな“感じ方”でできていますから。

仕組みの違い:「鏡あり」か「鏡なし」かが分かれ道
カメラの話をするとき、まず出てくるのが「一眼レフか、ミラーレスか」という二択という人もいるかもしれません。
でも正直な話、初めて聞いたときは「ミラー? レス? 何を失ってるの?」と思いました。
そう、ミラーレスは“ミラーがレス(=ない)”。
つまり、一眼レフが“ミラーあり”なら、ミラーレスは“ミラーなし”。
ここまで読んで「なるほど、だから何?」と思ったあなた、いい質問です。
その“鏡の有無”こそが、カメラの心臓部を決めるんです。
一眼レフの中では、鏡が働いている
一眼レフのボディの中には、小さな鏡が隠れています。
レンズから入ってきた光を反射して、上にあるプリズムに送り、ファインダーに届ける仕組みです。
つまり、あなたがファインダーをのぞくときに見ているのは、電子画面ではなく“現実そのもの”。
まるで「世界をそのまま覗き込んでいる」ような感覚です。
そしてシャッターを切る瞬間、あの「カシャッ!」という音とともに鏡が上がり、光が一気に撮像素子(センサー)に届く。
これが一眼レフの快感。
少し大げさに言えば、「鏡が跳ね上がるたびに魂が抜ける感じ」です。
ミラーレスは“鏡を取っ払って、映像で見せる”
ミラーレスはこの鏡を思いきって取り除きました。
レンズから入った光はそのままセンサーに届き、電子信号に変換されます。
そしてモニターやEVF(電子ファインダー)に映像として表示される。
つまり、あなたが見ているのは「現実」ではなく「現実を電気で再現したもの」。
でもそのおかげで、露出もホワイトバランスも“仕上がりのまま”確認できる。
「撮ってみないと分からない」時代から、「撮る前に分かる」時代に変わったんです。
ファインダーの見え方で性格が出る
「純喫茶の窓越しに外を眺めたい人」は一眼レフ。
「カフェのWi-Fiを使って作業したい人」はミラーレス。
そんな違いに近いかもしれません。
✅ 一眼レフは“鏡あり”。生の光をそのまま見られる。
✅ ミラーレスは“鏡なし”。撮る前から仕上がりがわかる。
✅ 見え方の心地よさは一眼レフ、便利さはミラーレス。
機能面の違い:AF・連写・手ぶれ補正・静音性
カメラというのは不思議なもので、
「機械」なのに、撮る人の性格がそのまま写る気がします。
ピントを合わせるスピードにこだわる人。
音を立てたくない人。
“止まっている時間”すら撮りたい人。
そんな欲望たちが、結局「どっちの方式を選ぶか」に現れるんです。
AF(ピント合わせ):脳の場所が違う
一眼レフは“二階建て構造”です。
ピント合わせをするのは、撮像センサーとは別のAFセンサー。
光が鏡で分かれ、その一部が下に送られてピントを計算します。
つまり、撮る瞬間の頭脳(AFセンサー)と、絵を描く手(撮像センサー)が別々に存在しているようなもの。
この方式は中央付近のピントがとても正確で、スポーツや望遠ではまだ根強い人気があります。
一方、ミラーレスは“ワンルーム構造”。
撮像センサーの上で直接ピントを測る。
だから「見ている場所=写る場所」が完全に一致。
しかも、被写体認識機能(人物・動物・乗り物など)と組み合わさり、動く被写体の追従がめっぽう強い。
例えるなら、一眼レフは「職人が尺で測ってから木を切る」。
ミラーレスは「レーザーで自動カット」。
どちらも正確だけれど、速度と柔軟性がまるで違うんです。
連写性能:時間を刻むリズム
かつては“一眼レフの連写こそ神”でした。
しかし、鏡が上下するという宿命ゆえ、どうしても一瞬の“暗転”が起きてしまう。
ミラーレスがそれを克服したのは、電子シャッターの進化です。
ブラックアウトフリー、つまり「撮っているのに画面が消えない」。
さらにグローバルシャッター搭載機では、歪みのない超高速撮影が可能。
120コマ/秒という世界は、もはや“時間のスローモーションを操る遊び”です。
手ぶれ補正と静音性:夜を味方にする機能
ボディ内手ぶれ補正(IBIS)は、ミラーレス時代の功労者です。
一眼レフではレンズ側に頼るしかなかった補正が、いまやボディごと揺れを打ち消す。
「単焦点で夜景を撮りたい」「動画も撮る」という人には、もはや必須機能になりました。
そして静音撮影。
ミラーレスは電子シャッターで完全無音。
ピアノ発表会や結婚式、図書館のような空間でも“気配だけ残して撮る”ことができます。
あの「カシャッ」が好きな人には少し物足りないかもしれませんが、
“沈黙のシャッター”は撮影者の新しい美徳です。
✅ AFはミラーレスが最新技術で優勢。追従も速い。
✅ 連写・ブラックアウトフリー・歪み軽減もミラーレスが進化中。
✅ 一眼レフは電池持ちと安定した構えやすさが今も魅力。
✅ 静かな現場ではミラーレスの“無音撮影”が強い味方。
用途別で見る「どっちを選ぶべき?」
カメラを選ぶとき、人はだいたい「自分が何を撮る人間なのか」を忘れがちです。
かくいう私もそうでした。
“スペック厨”という沼に落ち、夜な夜な比較表をにらみつけ、
気づけば撮っていたのは「机の上の比較表」だけ。
でも本当は、撮る対象が先にある。
カメラはその次なんです。
子どもの行事・運動会・発表会
会場がざわつく中、我が子がステージの中央へ。
この瞬間に、電子シャッターの“無音”ほどありがたい機能はありません。
ミラーレスの被写体認識AFは、まさに“親の味方”。
人の顔を覚えて、瞳を追い、走り回ってもピントを外さない。
しかも高感度撮影も得意で、体育館の暗さにもめげません。
最近では、エントリークラスの機種でもこの“人物認識+瞳AF”が標準装備。
つまり、“撮れない理由”がほぼなくなった時代です。
2025年現在、メーカーの新製品の多くはミラーレス中心。
親の応援席に並ぶカメラも、気づけばほとんどがミラーレスになりました。
つまり、「静かに・確実に・速く」撮るならミラーレス一択です。
風景・スナップ・旅の途中
一方、旅の途中で立ち止まり、夕暮れの光を眺めながらシャッターを切る。
この時間に必要なのは速度ではなく“心の呼吸”です。
一眼レフの光学ファインダーをのぞくと、そこには加工のない世界が広がります。
EVFでは感じられない“空気の揺らぎ”や“色の温度”が、そのままの形で届く。
電池が長持ちするのも、地味ながら旅先では頼もしい。
一眼レフの新モデルは少なくなりましたが、名機たちは今も現役。
中古市場では整備済みの良品も多く、“光学で撮る喜び”を味わいたい人には、
いまなお十分な選択肢が残っています。
つまり、「ゆっくり・正確に・じっくり構える」なら一眼レフが気持ちいい。
動画・Vlog・配信
もしあなたが動画をメインに撮るなら、迷う必要はありません。
ミラーレスの天下です。
4K、6K、8K。
聞くだけで胸がいっぱいになる数字たちが、いまやエントリーモデルにも当たり前に搭載されています。
被写体認識AFとIBIS(ボディ内手ぶれ補正)の組み合わせで、
まるでジンバルを使っているような滑らかさが得られる。
YouTubeや配信の世界では、**「絵作りよりも、撮り続けられること」**が大事。
その点、ミラーレスのオート性能は“思考の速さで動くカメラ”です。
レンズ資産がある人
これは“お金の話”です。
昔からキヤノンやニコンの一眼レフを使ってきた人なら、
EFやFマウントのレンズをどうするかが悩みのタネ。
ここで救世主となるのが純正アダプター。
キヤノンならEF→RF、ニコンならF→Z。
これを使えば、手元のレンズを新世代のボディでも活用できます。
ただし、対応範囲やAF連動の制限は必ずメーカー公式の互換表で確認を。
「動かないレンズ」はただのオブジェになります。
✅ 子どもの行事・動体=ミラーレス(静かで速い)
✅ 風景・スナップ=一眼レフ(見え方と電池持ち)
✅ 動画・配信=ミラーレス(AFと安定性)
✅ レンズ資産重視=アダプター活用で橋渡し
さいごに:あなたに合うのはどちらか?
ここまで読んできたあなたは、すでに気づいているかもしれません。
カメラ選びって、スペックじゃなくて性格診断なんです。
速さを求める人。
静けさを求める人。
そして、“撮ることそのもの”を楽しみたい人。
この三者が一緒のカメラにたどり着くはずがありません。
ミラーレスは「今を撮る人」の道具
ミラーレスは、まさに現代のカメラです。
AFの速さ、手ぶれ補正、動画対応、そして静音性。
どれも「撮り逃さないこと」に特化しています。
被写体が動いても、光が変わっても、
その場で“失敗を修正できる安心感”。
これは、技術の進化が人にくれた「撮る自由」だと思います。
だからこそ、日常や行事、Vlog、SNS――
今この瞬間を記録する人にはミラーレスが最高の相棒です。
一眼レフは「撮る喜びを味わう人」の道具
一方、一眼レフはちょっと頑固な相棒。
重い、でかい、音がする。
でも、その全部が“撮る儀式”の一部なんです。
光学ファインダーをのぞいた瞬間に、世界が“電気の前”に戻る。
EVFでは得られない「空気の奥行き」と「時間の手ざわり」。
それを味わえるのが、一眼レフという文化の本質です。
2025年の今、新製品こそ少なくなりましたが、
「撮ることそのものを愛する人」にとって、
このスタイルはまだ終わっていません。
そして最後に
結局のところ、どちらを選んでもいいんです。
写真がうまくなるかどうかは、カメラじゃなくて“あなたの目”が決めるから。
もし迷ったら、こう考えてください。
速さで選ぶならミラーレス。
感触で選ぶなら一眼レフ。
それでもまだ決めきれない人は、店頭で一度“のぞいて”みてください。
その瞬間、きっとあなたの心がどちらかに動きます。
カメラ選びは恋と同じ。
理屈より、“気持ちよく撮れる相手”を選ぶのがいちばんです。
✅ まとめ:一言でいうと…
・“いまを逃したくない人”にはミラーレス。
・“光を味わいたい人”には一眼レフ。
・どちらを選んでも、写真はあなたの手の中にある。
本記事の参照情報(出典整理)URL一覧(2025/11/02時点)
カメラ構造・技術仕様
メーカー方針・市場動向
- Canon公式発表:「EOS-1D X Mark IIIが最後のフラッグシップ一眼レフ」
- The Verge:Canonが一眼レフからミラーレス中心へ移行する背景
- Nikon公式声明:「一眼レフ撤退報道は推測」
- TechRadar:2025年ニコンZマウント新レンズ展開
AF/連写/手ぶれ補正 技術
レンズ互換性・アダプター情報
免責・注意事項