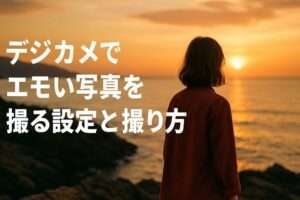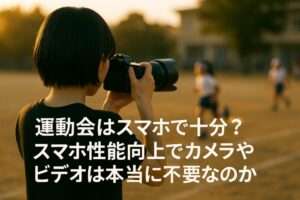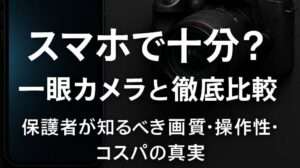体育館の照明は、いつも「明るいふり」をしています。
目で見ると普通に見えるのに、カメラを向けた途端、写真はすぐに暗くなり、動きは線になります。
走る脚も、跳ねる腕も、ボールさえも形を保てない。
その瞬間、「撮れていない」という事実が、胸の奥に重く落ちる。
私もそうでした。
試合中は夢中で撮り続けて、撮れているつもりだったのに、
あとで拡大してみると、どの写真も止まっていない。
その原因は、技術不足でもセンスでもありませんでした。
順序を知らなかっただけでした。
動きを止めるには、シャッタースピードを先に決める。
明るさはISOに任せる。
ただし、ISOには上限をつけて画質を守る。
この「考え方の順番」を理解した瞬間から、体育館の写真は変わりました。
止まる。
明るさが破綻しない。
色も安定する。
写真に「意図」が生まれたのです。
この記事でわかること
・体育館で写真が暗くブレてしまう本当の理由
・「シャッタースピードを先に決める」と止まる理由
・Auto ISOに“上限”をつけて画質を守る具体的な設定方法
・フルサイズ / APS-C / マイクロフォーサーズでの現実的なISO上限
・バスケ・バレー・バドミントン・ミニバスでのシャッタースピード基準
・体育館特有のLEDちらつきを抑える設定の考え方
・試合前に1分でできる「現場調整の手順」
この記事が「センスではなく設計で撮れるようになる」ための参考になれば幸いです。

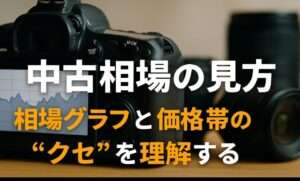
体育館の暗所で写真がブレる理由
 でん子
でん子何を当たり前のことを・・・



しかし、目で見えてしまう分、
「実は暗い」と気が付くのは難しいものです。
子どもが走っているのも、
表情が引き締まっているのも、普通に見えます。
「暗い場所」という実感はありません。
しかし、カメラはまったく同じ光を受け取っているのに、暗く写ります。
ここで、目とカメラが“同じ世界を見ていない”ことがはっきり表れます。
人間の目は、その場に合わせて勝手に明るさを調整しているからです。
カメラはそれをしません。
入ってきた光の量で、そのまま描きます。
つまり、
「見えている」ことと「写る」ことは別の話です。
これは感覚の問題ではなく、ただの事実です。
そして、体育館のスポーツは速い
走る速度。
跳ぶ瞬間。
シュートの腕の振り。
どれも、思っているより速い。
「見える」から、止まっているように感じているだけです。
実際には、動きは常に流れています。
光が少ない場所で、動きが速い。
ここに、シャッタースピードが遅いという条件が重なると、
写真は「形」ではなく「通過の記録」になります。
脚は線になり、
腕は二重に見え、
ボールは丸ではなく、軌道だけが残ります。
これは失敗ではなく、
単に 止められていない のです。
優先するべきは、明るさではない
明るさはあとで調整できます。
ノイズはあとで処理できます。
しかし、
動きは、その瞬間にしか止められません。
だから順番は、こうなります。
動きを止めたい → シャッタースピードを先に決める
明るさ → ISOに任せる
ただし → 画質が崩れないように上限を決める
これは「上手い人がやっている方法」ではなく、
止まる写真を撮るときの、ただの前提条件です。
ここまでで、
なぜ体育館で写真がブレるのかは、もう説明できています。
光が足りない
+
動きが速い
=
シャッタースピードが
足りていないと、残像になる
この一点です。
SS固定+Auto ISO上限という発想
体育館で写真を止めたいなら、最初に決めるべきはシャッタースピードです。
ここを後回しにすると、どれだけ設定をいじっても「残像」から抜け出せません。
暗い場所で動いているものを撮るとき、
「明るくする」より先に、
「止める」ことを選ばなければいけません。
この順番が、結果を左右します。
動きを止める手段はシャッタースピードしかない
走る 跳ぶ 振る 投げる。これらは、視覚上は“見える”ので同時に止められるような気がします。
しかし実際には、動きは常に流れています。
写真において、
動きを止めるための要素はシャッタースピードひとつです。
露出補正でも、明るいレンズでも、高価なカメラでも代わりにはなりません。
ここはごまかせません。
明るさは ISO に任せるという考え方
「止める」ためにシャッタースピードを速くすると、画像は暗くなります。
これは自然な現象です。
そこで明るさは ISO に任せます。
ISO は、光が少ない状況でも明るさを持ち上げる役割です。
「暗所で止める写真」を成立させるために、ISO は必要な存在です。
問題は、
ISOを上げればノイズが増えるという点です。
だから、
ISOには“上限”を決めます。
これが Auto ISO 上限の役割です。
ISO上限を決めると「止まるけれど破綻しない」ラインが作れる
ISOを無制限に上げると、画像は荒れます。
逆に、上限を低く設定しすぎると、写真は暗く沈んでいきます。
だから、ここで必要なのは
**「あなたのカメラが耐えられる上限を知ること」**です。
たとえば現実的には、
フルサイズ:6400〜12800
APS-C:3200〜6400
マイクロフォーサーズ:3200(必要に応じて6400)
このあたりが、破綻する前に踏める範囲になることが多いです。
機材の性能差や世代差はありますが、
ここで重要なのは「無制限に上げない」ことではなく、
「止めるために上限を使う」ことです。
止まっていない写真は、明るさより先に解決する必要があります。
だからこそ、
「動きを止める → 明るさはISO → 画質は上限で守る」
という順序が基準になります。
ここまでで、“考え方の設計図” はできました。
次は、
この設計図を 実際の設定に落とし込む 段階へ移ります。
体育館で最初に設定すべきシャッタースピード
体育館で写真を止められるかどうかは、最初にどのシャッタースピードを選ぶかで決まります。
ここを外すと、ISOをどう調整しても、レンズがどれだけ明るくても、歩留まりは上がりません。
体育館は光が足りない。
そして、スポーツは動きが速い。
この条件下では、シャッタースピードは「迷わず速く」から始めます。
目安になる「出発点」は 1/800 秒
このあたりは、止まるときもありますが、止まらないときのほうが多い速さです。
動きが線になる写真が続いていたのであれば、
それはカメラが悪いのでも、あなたが下手なわけでもありません。
シャッタースピードが足りていなかっただけです。
だから、まずは 1/800 秒を出発点にします。
競技ごとの「止まる速さ」はこう変わる
バスケット
→ 1/800 ~ 1/1000 秒
シュート・リバウンド・速攻の動きが速いため、1/800 が下限として安定します。
バレーボール
→ 1/800 秒前後
スパイクの一瞬は速いが、打点前後に“止め所”があるため 1/800 から始められます。
バドミントン
→ 1/1000 ~ 1/1250 秒
シャトルは想像より速く、軌跡になりやすいので余裕を持って速めから入ります。
ミニバス(低学年)
→ 1/640 ~ 1/800 秒
体の移動そのものはやや遅いが、手とボールの速度は速いので 1/800 に近づけます。
ここで重要なのは、
「止めたい動き」基準で速さを決めるということです。
暗い体育館でどうしても光が足りないとき
ここで多くの人が「シャッタースピードを下げる」方向へ向かいます。
ですが、ここが分かれ目です。
シャッタースピードを下げると、止まらなくなる。
つまり、ここで下げると 目的そのものを捨てることになります。
下げるべきは、撮影距離・構図・立ち位置です。
遠くを狙うほど必要なシャッタースピードは速くなります。
近づける場所に少し移動するだけで、必要な光量は変わります。
レンズでもなく、カメラでもなく、立ち位置が画質を決める場面は多いです。
オススメ体育館シャッタースピード表
| 対象・状況 | 推奨シャッタースピード | 理由・背景 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 基本の出発点 | 1/800 秒 | 体育館の動作は見た目以上に速いため、ここから始めると歩留まりが急に安定しやすい。 | ここを基準に、競技と動きに応じて上下させる。 |
| バスケットボール | 1/800 ~ 1/1000 秒 | シュート、リバウンド、ドライブなど動きにピークがあるため止めやすい帯がこの範囲。 | 速攻が多い試合は 1/1000 側が安定しやすい。 |
| バレーボール | 1/800 秒 前後 | スパイクには速さがあるが、打点直前に“止まりかける”瞬間がある。 | ライトが暗い体育館では 1/640 まで妥協する場合もある。 |
| バドミントン | 1/1000 ~ 1/1250 秒 | シャトルが高速で、軌跡になりやすい。止め所はあるが速めの方が成功率が高い。 | 暗い体育館では ISO 上限が先に効くため、構図と距離の調整が必要。 |
| ミニバス(低学年) | 1/640 ~ 1/800 秒 | 体全体の移動はやや緩やかだが、手とボールの速度は速い。 | 結局は 1/800 に近づけたほうが止まりやすい。 |
| 暗い体育館で光が足りない場合 | シャッタースピードは下げない | SS を下げると「止まる写真」という目的そのものが失われる。 | 明るさ不足は ISO と距離(立ち位置)で対処する。 |
ISO上限は「止める」と「画質」を同時に成立させる境界線
ここまでで、体育館では シャッタースピードを先に決める ことが明確になりました。
では、その速さで撮ったときに足りない明るさはどうするのか。
答えは ISO に任せるです。
ただし、ISOは上げすぎれば画像が荒れます。
だから、上限を決めてコントロールする必要があります。
ここが「止まる一枚」を取れるかどうかの、分水嶺になります。
ISOは「光を足す」のではなく「足りない光を持ち上げる」
ISOは、光そのものを増やすわけではありません。
入ってきた光を 増幅する処理 です。
光が少なければ、ノイズが増えます。
ただし、体育館の撮影で問題になるのはノイズそのものではありません。
止まらない写真(残像)よりは、ノイズがある写真の方が圧倒的に見られる。
ここで多くの人が誤解しています。
・「ノイズは怖い」
→ しかし、止まらなかった写真はそもそも作品にならない
優先順位は明確です。
ISO上限の現実的な基準値
ここは、センサーサイズと世代を踏まえた「現実的な可動範囲」です。
| センサー | 初期設定の上限 | 暗い体育館での現実的上限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| フルサイズ | 6400 | 12800 | 最新世代は12800でも後処理で十分仕上がることが多い。 |
| APS-C | 3200 | 6400 | 6400までは「作品」として成立するラインに収まることが多い。 |
| マイクロフォーサーズ | 3200 | 6400(必要なら) | 強い手ぶれ補正はあるが、動体には効かないのでSS優先は変わらない。 |
ここで大切なのは、
ISO上限は固定ではなく、体育館の明るさによって動かすということです。
「うちの体育館はいつも暗い」
→ 上限を一段上げる
「大会会場で照明が強い」
→ 上限を一段下げる
この柔軟性が、現場での歩留まりを決めます。
「ノイズが怖い」を乗り越える視点
ノイズは、現像で整えることができます。
最近のノイズリダクションは、昔とは比べものになりません。
しかし、止まらなかった写真は 現像では絶対に直りません。
ここが核心です。
止める → あとで整える
止まらない → 何をしても戻らない
だから、
**ISO上限は「止まるために使う枠」**です。
LEDフリッカー対策は「止まる」次に必要な安定要素
体育館で撮ると、止まったのに写真が安定しないことがあります。
明るさがコマごとに揺れたり、色がわずかに変わったりする。
これは、LED照明の点滅が原因です。
LEDは、人間の目では見えない速さで明滅しています。
その周期とシャッタースピードのタイミングがずれると、
写真の一部だけ暗くなったり、色がずれたりします。
この現象が フリッカー です。
止まっているのに、質感が不安定になる。
これが、体育館の撮影を難しくしているもう一つの理由です。
フリッカー対策の基本は「アンチフリッカー撮影」をオンにする
| ブランド | 設定名称 | 特徴 |
|---|---|---|
| Canon | アンチフリッカー撮影 | 点滅周期に合わせて撮影タイミングを整える |
| Nikon | フリッカー低減 | 120Hz/100Hzの揺らぎを抑える |
| Sony | アンチフリッカー撮影 | 機械シャッターで効果が安定しやすい |
| Fujifilm | Flicker Reduction(全コマ / 初回のみ) | 連写速度がやや変化する可能性がある |
| OM SYSTEM | アンチフリッカー撮影 + Flicker Scan | 画面上で帯を見ながらシャッタースピードを微調整できる |
重要なのは とにかく“オンにする”こと です。
これだけで、コマごとの明るさと色の安定性が大きく改善します。
「止まる写真」でも安定しないと“良い写真”に見えない
人は、明るさの差や色の差に非常に敏感です。
ほんの少し違うだけで、画が「不安定」に見えます。
止まっているのに、なんとなく良く見えない写真。
その多くは、フリッカーによる安定不足です。
つまり、
止める → シャッタースピード
成立させる → ISO上限
安定させる → アンチフリッカー
という順番になります。
もしアンチフリッカーをオンにしても帯が消えない場合
体育館の照明によっては、点滅の周波数が一般的な 100 / 120Hz と微妙にずれていることがあります。
この場合は、
・シャッタースピードを細かく刻む
・天井の照明をライブビューに入れて、帯が消える速度を探す
という方法が効果的です。
Sony と OM SYSTEM は、
「可変シャッター」「Flicker Scan」 によって
帯が見える状態のまま速度を調整できます。
この一手間が、最後の画質を決めるかもしれません。
立ち位置とレンズで“必要なISO”は変わる
体育館では、設定だけで全てを解決できるわけではありません。
同じカメラ・同じレンズ・同じ設定でも、立ち位置が変わるだけで写真は変わります。
なぜか。
光量と必要なシャッタースピードは、距離と焦点距離に連動しているからです。
遠い被写体は、速く動いて見える
例えば、コートの端から端を狙うとき。
実際の動きより、画面上の移動量が増えます。
このとき、必要なシャッタースピードは自然と上がります。
逆に、近くで撮ると動きは遅く見えるため、
同じ 1/800 秒でも 止まりやすく なります。
つまり、
焦点距離が長くなるほど、必要な光は増える
70-200mm の望遠レンズは、体育館撮影の定番です。
しかし、長くなるほど被写体の動きが大きく写るため、ブレに敏感になります。
同じ 1/800 秒でも、
・70mm → 止まりやすい
・200mm → 伸びやすい
という差が生まれます。
つまり、
だから、立ち位置は“画質の設定項目”の一つ
設定画面には存在しないのに、
立ち位置は ISO を下げるための最も強い手段です。
レンズでも、カメラでもなく、
「どこから撮るか」が
画質を決めることがある。
これを理解して動ける人は、
暗い体育館でも作品として成立する写真を残せます。
実践で役立つ立ち位置の例
| 状況 | 良い立ち位置 | 理由 |
|---|---|---|
| バスケット | ベースライン横(リング横の高さ) | 動きの方向とスピードが読みやすく、止め所が生まれやすい |
| バレーボール | ネット脇のサイドライン寄り | スパイク・ブロックの「作り」が見える |
| バドミントン | コート後方のやや低い位置 | シャトルの頂点と沈む軌道が作りやすい |
いずれも、共通点はひとつです。
これが、結果として ISOと画質を守る ことにつながります。
まとめ
体育館に入ったら、まずこの3ステップ
モードを M にする
シャッタースピードを 1/800 に設定
(競技に応じて 1/800〜1/1000 へ微調整)
絞りは開放(F1.8〜F2.8系)
ここまでで「止める」ための基準が整います。
次に、明るさを“ISOに任せる”
ISOは Auto にする
ISO上限を設定する
| センサー | 上限の目安 |
|---|---|
| フルサイズ | 6400(暗いなら12800) |
| APS-C | 3200(暗いなら6400) |
| MFT | 3200(状況によって6400) |
ここで 明るさは自動で持ち上がるようにします。
止める → ISO で補う → 上限で画質を守る、という構造が完成します。
次に、画の“安定”を作る
アンチフリッカー撮影をオンにする
(各社で名称は違うが、役割は同じです)
これで、コマごとの明るさ・色のブレが抑えられます。
動きの理解と立ち位置で、ISOをさらに下げる
遠くを撮ると ISO が上がる → 近づける場所を探す
望遠端より、少し短めの焦点距離の方が止まりやすいことを意識する
設定を変えずに画質が変わる部分です。
全体の流れ
止めたい → SSを決める
足りない → ISOに任せる
荒れさせない → ISO上限で囲う
揺れさせない → アンチフリッカーをオンにする
そして、
さらに良くしたい → 立ち位置と焦点距離を変える
これが体育館の「止まる一枚」の実践手順です。
最後に
体育館は、目には明るく見えます。
しかしカメラには「暗い」と言われます。
ここで最初に心が折れます。
でも、落ち込む必要はありません。
あなたの目が優秀なだけです。
カメラは正直者なだけです。
動きが速いなら、シャッタースピードを速くする。
暗ければ、ISOに頼る。
荒れすぎないように、上限だけ決めておく。
こう書くと、まるで料理のレシピみたいですが、実際そうです。
止める
明るくする
守る
順番にやるだけで、体育館は急に「撮れる場所」に変わります。
そして止まった一枚は、
「なんとなく撮れた写真」ではなく、
あなたが見ていた瞬間そのものになります。
難しい話ではありません。
ただ、順序があるだけです。
子どもの行事に初カメラデビューする人へ
体育館での撮影は、そもそもカメラ選びの段階で迷いやすい部分でもあります。
どの機種を選ぶと失敗しにくいのか、何を基準にすればいいのか。
そのあたりを、ゼロから順に整理した記事があります。
初めての一台を選ぶときに、遠回りをしないための考え方をまとめています。
必要であれば参考にしてみてください。




SDカードは「なんでもいい」ではありません
体育館撮影では、連写を使う場面が多くなります。
このとき、SDカードの書き込み速度が遅いと、決定的な瞬間でシャッターが止まってしまうことがあります。
「デジカメ用SDカードで「なんでもいい」はおすすめしない理由」
カード選びで避けたいポイントと、最低限の基準をわかりやすく整理しています。
撮影を安定させたいときに役立つ内容です。
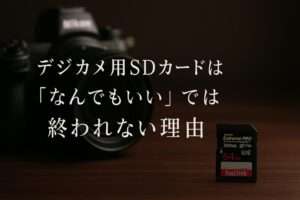
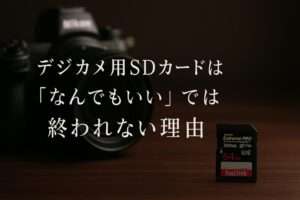
本記事の参照情報(出典整理)URL一覧
Canon|Anti-Flicker Shooting(EOS R7 マニュアル) Cam Start Canon
Canon|High-Frequency Anti-Flicker(EOS R6 Mark II マニュアル) Cam Start Canon
Canon|High-Frequency Anti-Flicker(EOS R5 Mark II マニュアル) Cam Start Canon
Canon Knowledge Base|EOS-1D X Mark III:Anti-Flicker Shooting キヤノンサポート
Sony Help Guide|Anti-flicker Shoot.(ILCE-7SM3) ヘルプガイド
Sony Help Guide|Anti-flicker Set.(ILCE-1) ヘルプガイド
Sony Help Guide|Anti-flicker と Var. Shutter の違い ヘルプガイド
Sony Help Guide|Anti-flicker Set.(ILCE-9M3) ヘルプガイド
FUJIFILM|X-T3 Firmware:FLICKER REDUCTION(ALL FRAMES/ FIRST FRAME/ OFF) Fujifilm X
FUJIFILM|X-T5 Firmware:FLICKER REDUCTION 関連更新 Fujifilm X
FUJIFILM|Feature Firmware 解説:Flicker Reduction のモード変更 Fujifilm X
OM SYSTEM Learning|Reducing Flicker Under LED Lighting(K/n Flicker Scan) learning.omsystem.com
OM SYSTEM Learning|Anti-Flicker Shooting(タイミング合わせ型) learning.omsystem.com
OM SYSTEM Learning|ISO-A Upper/Default(Auto ISO の上限設定) learning.omsystem.com
Nikon Online Manual|Flicker Reduction Shooting(Z6II/Z7II) onlinemanual.nikonimglib.com
Nikon Online Manual|High-Frequency Flicker Reduction(Z6III) onlinemanual.nikonimglib.com
Nikon Online Manual|ISO Sensitivity Settings:Minimum shutter speed(Z9) onlinemanual.nikonimglib.com
Nikon Online Manual|ISO sensitivity settings:Minimum shutter speed(Z fc) onlinemanual.nikonimglib.com
NikonUSA Learn & Explore|Understanding Auto ISO(最小シャッタースピードの考え方) ニコン
Digital Photography School|Tips for Indoor Sports Photography(SS の起点) Digital Photography School