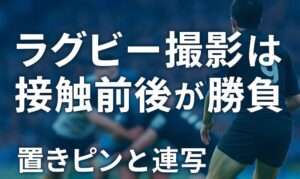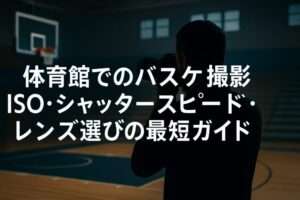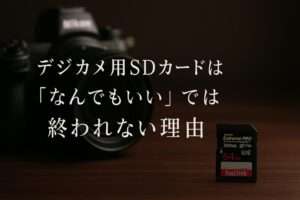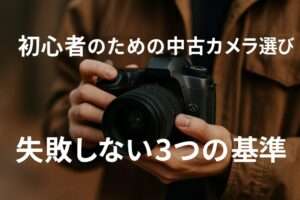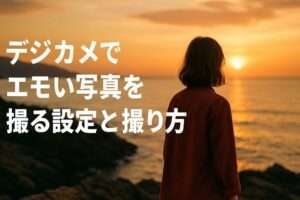体育館でバドミントンを撮影しようとすると、想像以上の速さにまず圧倒されます。
私自身、最初は「スポーツ撮影なら何とかなるだろう」と軽く考えていました。
ところが、撮ってみるとシャトルは尾を引いて消え、選手の表情もブレて判別できません。
背景には観客や派手な広告が入り込み、せっかくの一瞬が台無しになることが何度もありました。
 バテ男
バテ男あの頃は設定の基本を知らずに何度も失敗しました・・・



速さに目を奪われて、何から手を付けるべきか分からなくなりますよね。
その経験を重ねて初めて、「まずはシャッタースピードを基準に決める」という大切さに気づきました。
そしてISOや絞りで露出を支え、背景をあらかじめ整理することで、ようやく理想に近い一枚を撮れるようになったのです。
この記事では、同じ壁にぶつかっている方が遠回りをせずに済むよう、私が試行錯誤してつかんだ撮影の要点をまとめました。
バドミントンの撮影で悩んでいらっしゃる方のお役に立てれば幸いです。是非最後までご覧ください
この記事でわかること
- バドミントン撮影に必要なシャトル速度理解とシャッタースピード設定の基準
- 体育館という環境に合わせた露出とISO運用、明るいレンズの選び方
- AF設定やフリッカー対策で失敗を減らすポイント
- 背景処理で主役を際立たせる具体的なテクニック
- 試合中に役立つポジショニングと席替え戦略


高速シャトルを止めるシャッタースピードの基本
バドミントン撮影で最初に直面する壁は、肉眼では追えないほどのシャトルの速さです。
私も初めは1/500秒程度で十分だろうと考えていましたが、撮った写真を見返すとシャトルは線のように伸び、選手の表情もかすんでしまいました。



当時はシャッタースピードを軽く見ていたので、失敗が続きましたね。



実際に撮ってみると、想像を超える速さに驚きました。
バドミントンの速度を理解する
トップ選手のスマッシュは時速500kmを超えるとされ、一般の試合でもかなりの速度が出ます。
常にその速度というわけではありませんが、高速被写体を点像として止めるには、相応のシャッタースピードが必要になります。
1/1250秒を基準に上げ下げする
私は1/1250秒を「止めるための出発点」として設定し、状況に応じて調整するようにしました。



スマッシュやネット前のドライブは1/1600〜1/2000秒まで上げると安心ですよ。



躍動感を残したい場面では1/800〜1/1000秒に落とす方法もありますね。
完全に止める写真と、スピード感を残す写真。
ISOとレンズの明るさで支える
体育館の照明は明るくないため、ISOを4000〜5000程度を起点に、必要に応じてさらに上げることもあります。
開放F2.8のズームやF1.8の単焦点を使えば、高速シャッターでも被写体をしっかり捉えやすくなります。



まずは「止める」ことを優先し、ISOで露出を稼ぐ方が歩留まりが高いですね。



後処理でノイズを抑えれば、結果として良い写真になります。
この基本を守るだけで、ブレだらけだった私の写真は見違えるように変わりました。
脚注:歩留まりについて
バドミントン撮影における「歩留まり」とは、撮影した枚数のうち、ピントが合い構図も意図通りに仕上がった“使える写真”の割合を指します。
体育館のような照度の低い環境では、
・シャッタースピードを優先してISOが上がりノイズが増える
・AFが背景やネットに奪われる
・フリッカーによる露出ムラが発生する
といった要因で歩留まりが下がりやすい傾向があります。
歩留まりを高めるには、以下の工夫が有効です。
- シャッタースピードをまず1/1250秒に固定し、ISOで露出を確保する
- AF-C(AI Servo)で中庸のゾーンを選び、必要に応じて置きピンを併用する
- アンチフリッカー機能をONにし、副作用(レリーズ遅延や連写速度低下)を理解した上で活用する
このように、現場での設定や立ち位置の工夫が「歩留まり」向上のカギとなります。
室内ならではの露出と機材選び
体育館での撮影は、外光に頼れない分だけ露出設計が難しくなります。
私も最初の頃は、シャッタースピードを優先するあまり暗い写真を量産し、ISOを上げることに不安を覚えていました。



当時はISOを上げるのを怖かったんですよね



ええ、でも今のカメラなら高感度でも十分実用的だとわかりました。
F2.8級レンズとISO運用
ISOは4000〜5000を起点に、会場や機材によってはさらに上振れすることもあります。
開放F2.8のズームやF1.8クラスの単焦点レンズを使えば、シャッタースピードを1/1250秒に保ちながら露出を確保しやすくなります。



通しF2.8の70-200mmズームはバランスが良く、どの距離からでも対応しやすいですね。



固定席なら85mmや135mmの単焦点も背景分離に強いです。
AF設定とフリッカー対策
被写体を追い続けるためにはAF-C(AI Servo)を使い、中庸のゾーンを選ぶのが実践的です。



ネットや照明にAFが奪われやすい場面では、置きピンを併用すると安定します。



それにバックボタンAFを活用すると構図とピント操作を分けられて便利ですね。
体育館では蛍光灯やLEDによるフリッカーが起きやすく、アンチフリッカー機能をONにすることが欠かせません。
ただし、レリーズ遅延や連写コマ速低下といった副作用があるため、重要な場面ではその影響を考慮しましょう。



静音が必要で電子シャッターを使う場合は、可変シャッター機能で縞を調整し、消えなければメカシャッターに戻すと安全です。



そうですね。機能の限界を理解しておくことでトラブルを防げます。
高感度に耐えられるカメラと明るいレンズ、そして適切なAFとフリッカー対策。
この三つを揃えることで、体育館という厳しい環境でも1/1250秒を守りながら、ブレない一瞬を確実に切り取ることができます。
背景処理で主役を浮かび上がらせるテクニック
バドミントンは被写体が小さく、動きが速いため、背景のうるささが写真の印象を大きく左右します。
私も初めの頃は、観客席や広告が目立ってしまい、主役が埋もれる写真ばかりを量産してしまいました。



背景を意識せずに撮ると、せっかく止めても主役がぼやけて見えるよね。



本当に。座席や角度を変えるだけで、こんなに違うとは驚きました。
背景を選ぶ三つのステップ
まずは座席の位置選びからです。
暗幕や観客の少ない側、壁面が遠い場所を狙うと、背景を暗く落としやすくなります。
次に被写体と背景の距離をできるだけ取ります。
距離が開くほど同じF値でもボケが大きくなり、主役が自然と際立ちます。
最後に長めの焦点距離を活かします。
画角が狭まることで不要な要素をフレーム外に追い出しやすくなり、圧縮効果で背景が整理されます。
ローポジションや暗背景づくり
低い位置から見上げるローポジションは、選手を大きく見せながら床や観客席をフレーム外に押し出す効果があります。
また、照明の角度を避けて天井梁など暗部を背景にすると、被写体の輪郭が際立ちます。



暗背景を作るには露出を下げるのではなく、席や角度で工夫するのがポイントですね。



そうですね。撮影前の席取りで七割が決まると言っても過言ではありません。
構図で背景を整理する
ラケットやシャトルが背景の明るい線と重ならないよう、体を小さく動かして角度を微調整します。
肩から上半身、ラケットヘッド、シャトルが同じフレームに収まる瞬間を狙うと、スピード感と構図のバランスを両立できます。
背景処理を「撮る前に決める」意識を持てば、編集での後処理に頼らなくても主役が引き立つ一枚が手に入ります。
実戦でのポジショニングと回遊術
撮影設定を完璧にしても、立ち位置を誤れば決定的瞬間を逃してしまいます。
私も初めは座った席から動かずに撮っていましたが、同じ角度ばかりで迫力が乏しく、写真に変化が出ませんでした。



立ち位置を変えるだけで、写真の印象は大きく変わりますね。



本当に。少し移動するだけで背景も構図も劇的に変わります。
立ち位置別の特徴
エンドライン延長上に立つと、スマッシュを正面から狙え、迫力ある一枚が撮れます。
ただしネット越しの手前の被写体が重なりやすいので、構図に注意が必要です。
サイドライン中腹ではラリーの全体を見渡せ、背景選びの自由度が上がります。
選手の駆け引きを捉えたり、球筋の流れを見せたりするのに向いています。
やや低い位置から撮ると、見上げる構図となり、床や観客席をフレーム外に押し出す効果があります。
ゲームごとの席替え戦略
試合が複数ゲームに分かれている場合、第1ゲームではエンド側でスマッシュの迫力を狙い、第2ゲームではサイドでネット前の攻防を捉え、第3ゲームでは逆サイドからバックハンド側の崩しを狙う。
このようにゲームごとに席を替えることで、多様な表情を写真に収められます。



もちろん大会によって観客が移動できるかはルールが異なりますから、主催者の規約に従う必要があります。



許される範囲で動くことで、撮れるカットの幅が大きく広がりますね。
まとめ
・エンドラインではスマッシュの迫力を、サイドラインでは試合の展開を捉える。
・ローポジションで背景を整理し、主役を引き立てる。
・複数ゲームを通して席替えを行えば、多角的な写真を残せる。



設定だけでは得られない「現場を読む力」こそ、バドミントン撮影の最終的な決め手です。



本当に、経験を重ねることで見えてくるものがありますね。
こうした実戦的なポジショニングと回遊術を意識すれば、同じ試合でも何倍もの表情を引き出せる写真が撮れるでしょう。
さいごに
バドミントン撮影は、単にカメラの設定を覚えるだけでは成果が出ないことを、私は何度も痛感してきました。



機材だけを揃えても、現場での工夫がなければ同じ失敗を繰り返してもったいないですよね・・・



その通りです。状況を読む力が最終的に写真の質を左右します。
これらの積み重ねこそが、ブレやノイズに悩まされていた過去の私を救ってくれました。



最初からこの基本を知っていれば、、、



でも失敗したからこそ、同じ悩みを持つ人に伝えられるなら幸いですね
今回紹介したポイントは、体育館でのスポーツ撮影全般にも応用できます。
さらに詳しい「体育館」撮影の基本については、「体育館」の記事も参考にしてください。
一枚一枚の試行錯誤が、必ずあなたの写真を進化させてくれるはずです。
参考サイト一覧
Canon 公式:アンチフリッカー撮影ガイド
https://www.canon.com.hk
Nikon 公式:オンラインマニュアル(フリッカー低減・AF設定)
https://onlinemanual.nikonimglib.com
Sony 公式サポート:可変シャッター・アンチフリッカー解説
https://www.sony.jp/support/
Digital Photography School:スポーツ撮影チュートリアル
https://digital-photography-school.com/
Photzy:背景処理と構図テクニック
https://photzy.com/
E-Squared Photography:暗背景づくりの実例
https://esquaredphotography.com/
Guinness World Records:バドミントンスマッシュ速度記録
https://www.guinnessworldrecords.com/
Yonex:バドミントンシャトル速度データ
https://www.yonex.com/
Nikon Professional Services:屋内スポーツ撮影の推奨設定
https://nps.nikonimaging.com/
Jeff Cable’s Blog:オリンピック撮影記録とレンズ選び
https://blog.jeffcable.com/