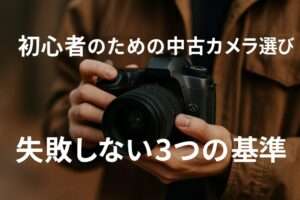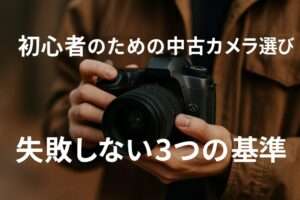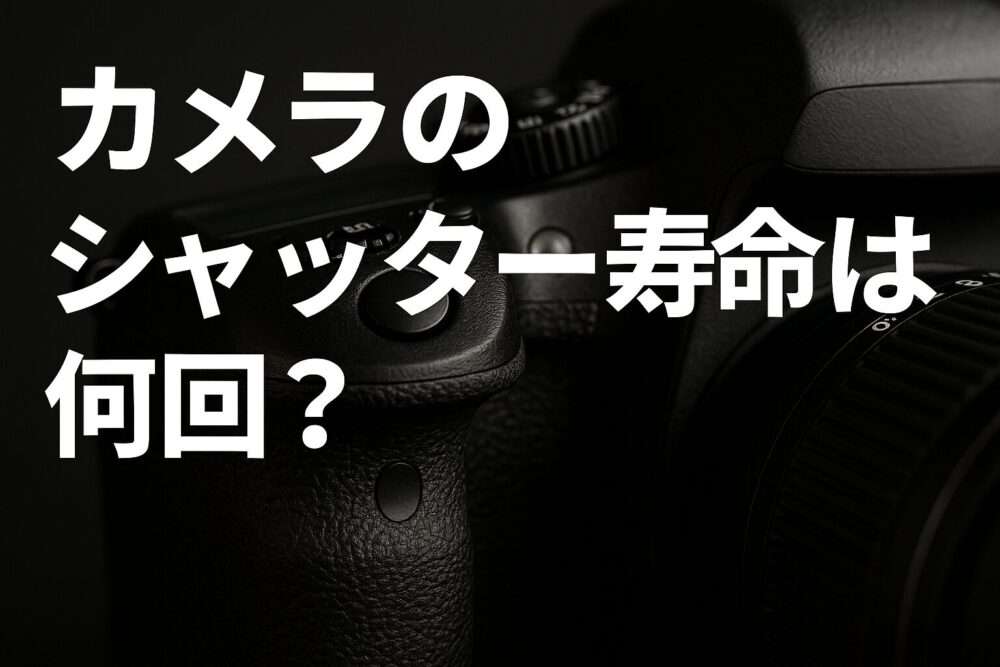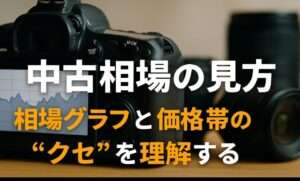ただ「目の前の一瞬を逃したくない」という思いだけで、毎日のようにシャッターを切っていたのです。
ところがある日、わが子の運動会。
ゴールテープを切る決定的な瞬間に、
突然シャッターが反応しなくなりました。
胸が凍りつくような数秒
二度と戻らない光景を
ただ見送るしかありませんでした__
 バテ男
バテ男皆さんが今お使いのカメラ、何回シャッターが押されたか把握していますか??



見た目がきれいなら安心だと思っていましたが、、、
「まだ大丈夫」と油断していると、大切な場面で突然動かなくなることもあるのです。
だからこそ、自分のカメラがあとどれくらい使えるのかを把握し、
修理か買い替えかを冷静に判断することが重要になります。
この記事を読めば、カメラのシャッター寿命を回数の目安から残寿命の計算方法、さらに修理と買い替えを見極める3段階の判断基準まで、一通り自分で判断できる知識を身につけることができます。
是非最後までご覧ください!
この記事でわかること
- シャッター寿命を判断するための回数目安
- 修理費用と買い替え費用の比較ポイント
- 実務に役立つ残寿命の計算手順
- 修理か売却かを決める3段階の判断方法
シャッター寿命を知るべき理由
シャッター寿命と耐久回数
カメラのシャッター寿命を語るうえで、
まず押さえておくべきはメーカーが公表している「耐久回数」の目安です。
これは保証された寿命ではなく、統計的にその回数までは正常に動作する確率が高いという設計上の指標にすぎません。
一般的にエントリー機や中位モデルでは 10万〜20万回 程度が一つの基準とされています。
一方で報道・スポーツ用途のフラッグシップ機では 40万〜50万回 といった耐久値が示されることも珍しくありません。
※一例です



この数値は「その回数で必ず壊れる」という意味ではないので注意しましょう



つまり、早く壊れる個体もあれば長く持つ個体もあるということですね。



その通りです。実際には10万回以下で故障する例もあれば、20万回を大きく超えても元気に動く個体もあります。
またミラーレス時代に入り、電子シャッターを主体に撮影している場合は機械的な摩耗がほとんど進みません。
ただし電子シャッター特有のバンディングやローリング歪みなど別の注意点もあり、「寿命を気にしなくてよい」と断言することはできません。
特に中古購入では、前オーナーがどの程度シャッターを切ったかが不明確な場合があります。
EXIFなどから回数を確認できる機種もありますので、購入前に調べておくと安心です。
このように公称値はあくまで目安にすぎません。
日常の撮影スタイルや中古購入時の確認次第で、実際の寿命は大きく変わることを覚えておきましょう。
EXIFでシャッター回数を確認する際の注意点
EXIF(Exchangeable Image File Format)は、撮影した写真データに自動的に記録される付帯情報のことです。
シャッターを何回切ったか(シャッター回数)を機種によってはこのEXIF内から読み取ることができます。
- 機種ごとの対応差
Nikonや一部のCanon機などはEXIFにシャッター回数が含まれていますが、すべてのメーカーや機種が対応しているわけではありません。 - ツール選び
ExifToolなど専用ソフトを利用するのが確実です。
無料のオンラインサービスもありますが、未加工の撮影ファイルをそのままアップロードする必要があり、個人情報やプライバシーに配慮して信頼できるサイトを選ぶことが大切です。 - 編集済みファイルでは確認不可
RAW現像や画像編集後に保存し直したファイルでは、EXIFの一部が消えていることがあり、シャッター回数が読めなくなる可能性があります。 - 中古購入時の確認
中古カメラを購入する際にシャッター回数を把握したい場合は、販売店に確認をお願いするか、購入前に試し撮りして自分でEXIFを調べると安全です。
このように、EXIFはシャッターの残寿命を推測する上で有効な手掛かりになりますが、機種依存やファイル状態による制限がある点を必ず理解しておく必要があります。
残寿命を見積もる手順
カメラのシャッター寿命を把握するには、「今どれだけ切ったか」を数値で確認し、残りを推定する必要があります。
これは単なる感覚ではなく、具体的な手順を踏むことで初めて見えてくるものです。
EXIFからシャッター回数を調べる
まずは撮影したばかりの未加工ファイル(RAWやJPEG)を用意します。
ExifToolなどの専用ソフトを使えば、対応している機種ならEXIFデータの中にシャッター回数が記録されており、これを読み取ることで現時点の総撮影枚数を確認できます。



確認する時は、編集前のファイルを必ず使ってください。編集済みだと回数が消えている場合があります。



購入時に試し撮りして、そのデータで調べれば安心できますね。
公称耐久回数から差し引く
メーカーが公表している耐久回数(10万、20万、40万回など)から、今確認したシャッター回数を差し引きます。
これで残りの「機械的に耐えうる回数」の目安が出ます。
もちろん統計上の目安に過ぎないため、早期故障や想定以上に長持ちするケースもあります。
年間撮影枚数で年数換算
自分が一年間にどれだけシャッターを切っているかを把握しておくと、残寿命を年数に換算できます。



例えば年間2万枚撮る場合、残り10万回なら約5年が一つの目安となりますよね。



電子シャッター主体で撮っているなら、機械式の摩耗はもっと少ないため、実質的にはこの計算より長く使える可能性もあります。



ただし電子シャッターにはバンディングなど別の制約があるので、完全に「寿命を気にしなくていい」とは言えませんね。



こうした手順を踏めば、自分のカメラがどれだけ安心して使えるかを数値で把握でき、修理か買い替えかを判断する大きな材料になりますね。
修理か買い替えかを判断する3段階フロー
シャッターの残寿命が見えてきたら、次は「修理するか、それとも買い替えるか」を冷静に決める段階です。
ここでは残りの耐久回数と利用状況を踏まえた三つのステップに分けて考えます。
第1段階:残寿命が十分な場合(公称の1/2未満)
公称耐久回数の半分にも達していないなら、基本的にまだ大きな心配は不要です。



この段階なら、電子シャッターを多めに使うなどして機械的な摩耗を抑えると、さらに安心して使い続けられますよ。



安心しました。まだしばらくは買い替えを考えなくてもよさそうですね。
撮影枚数が多くても、電子シャッター主体なら機械的摩耗はゆるやかです。
点検は必要に応じてで構いません。
第2段階:残寿命が気になり始めた場合(公称の1/2〜8割)
公称耐久回数の半分を超えるあたりから、次の大きな撮影イベント前には点検や修理見積もりを取っておくことをおすすめします。
中古市場での査定額が高いうちに売却して後継機へ移行するか、数万円程度のシャッターユニット交換で延命するか、選択肢を比べる時期です。
第3段階:寿命限界が近い場合(公称の8割超)
耐久回数の8割を超える、あるいは露出ムラや異音など寿命を思わせる症状が出始めたら、早めの判断が必要です。



仕事で使うなら、故障時の損失を考えて前倒しの修理かボディ入れ替えを検討しましょう。



趣味用途なら、壊れた時点で修理するという選択もありそうですね。
フラッグシップ機などはシャッターユニットを交換すれば、再び長く使える例もあります。
用途に応じて、修理費と買い替え費用を天秤にかけて決断するのが賢明です。
修理か買い替えかを判断する3段階フロー
| 判断段階 | 公称耐久回数の目安 | 推奨対応 |
|---|---|---|
| 第1段階:残寿命が十分 | 公称の1/2未満 | 継続使用 |
| 第2段階:残寿命が気になる | 公称の1/2〜8割 | 点検・修理見積を取得し、売却も検討 |
| 第3段階:寿命限界が近い | 公称の8割超 | 前倒しで修理またはボディ入れ替え |
さらに、カメラを手放すタイミングや次の一台を購入するタイミングを詳しく知りたい方は、
関連記事「カメラの買い時・売り時:イベント需要と価格の季節性」もぜひご覧ください。
中古相場の動きやイベント需要を踏まえた価格変動の傾向をまとめています。


修理費用と売却価値の現実
シャッター寿命を意識したとき、多くの人が最後に悩むのは「修理か売却か」です。
残寿命が分かったとしても、費用と再販価値の天秤をどうかけるかで結論は変わります。
シャッターユニット交換の相場と納期
国内でのシャッターユニット交換は、機種や症状によって差はありますが
2〜6万円前後 が一つの目安とされています。
納期はだいたい通常 1〜3週間程度が多いようですね。
ただし部品在庫や受付状況によって前後するため、事前に複数社へ見積もりを依頼することが大切です。



正規サービスだけでなく、独立系の修理業者も選択肢に入れると比較しやすいですよ。



費用感や納期がそれぞれ違うので、複数見積もりを取るのが安心ですね。
中古市場でのシャッター回数の評価
中古市場ではシャッター回数が少ない方が評価される傾向がありますが、実際の査定では外観の状態や付属品、保証の有無など複数の要素が影響します。
シャッター回数だけで価格が決まるわけではありません。
修理 vs 売却を決める最終ポイント
- 今後6〜12か月で重要な撮影案件があるか
- 中古相場と乗り換え差額のバランス
- シャッター以外に基板やIBISなど致命的な不具合がないか
これらを整理し、**「次の案件の重要度」「手元総費用(修理費 or 乗り換え差額)」「稼働率」**の三つを軸に決めると現実的です。



修理して使い続ける安心感も大事ですが、売却して新機種に移ることで得られる機能向上も見逃せませんね。



はい。費用だけでなく、今後の撮影スタイルや必要な機能まで含めて検討するのが一番後悔しない方法です。
さいごに
シャッター寿命は単なる数字ではなく、撮影スタイルや仕事の重要度と密接に関わっています。
「まだ大丈夫」と思い込んでいた私自身が、運動会の一瞬を撮り逃した悔しさは今でも鮮明です。



あの経験があるからこそ、残寿命を数値で把握して判断することの大切さを実感しますね。



私も、これからは撮影だけでなくカメラの状態を定期的に確認していこうと思います。
今回紹介した 残寿命の見積もり手順、3段階の判断フロー、そして 修理と売却の比較ポイント を押さえて、いざというとき慌てずに行動していきましょう。
カメラは思い出を刻む大切な相棒
シャッターという命を守るために、数字と根拠に基づいた判断を重ねて、撮りたい瞬間を確実に残していきたいですね。



ここからは他記事の紹介です!!
修理見積と売却査定を同時に取得して比較することで、撮影の安心と総費用のバランスを両立したい方はこちらへ!