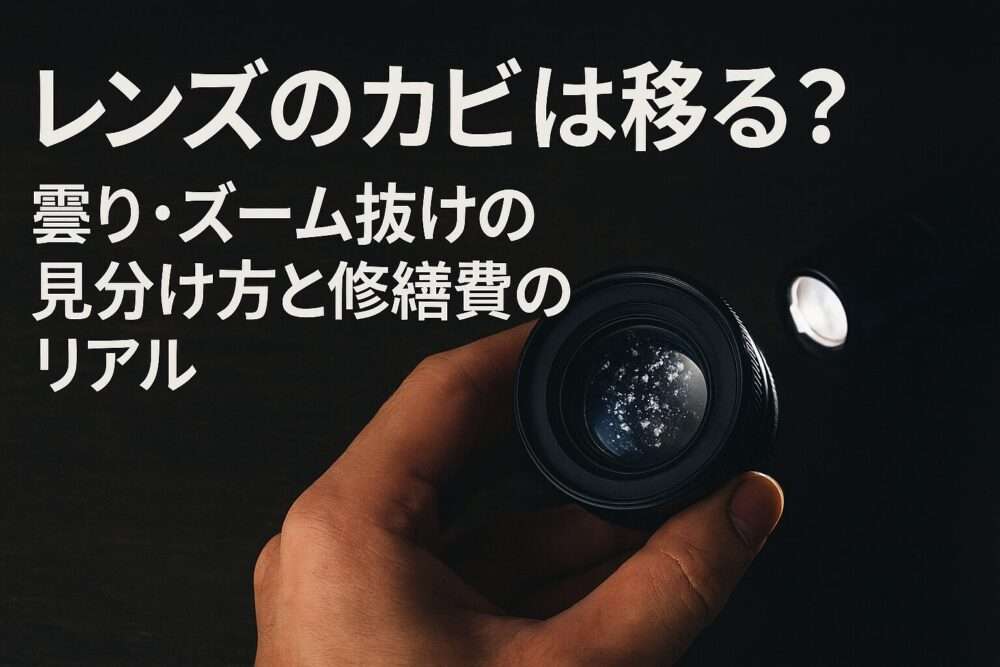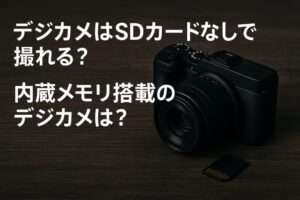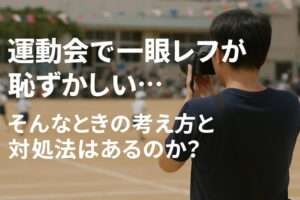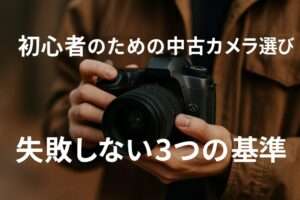中古レンズ棚の前に立つとき、人はなぜか自分の人生を思い返します。
きれいなものは高い。
安いものには理由がある。
これはレンズ棚に限らず、だいたいそうです。
しかし、その中でも 「安いのに妙に写りが良さそう」なレンズ というのが、たまにあります。
ガラス面はきれい。
外装もそこそこ。
なのに、値札がやたらと控えめ。
そのとき、心の奥で声がします。
「お前……何を隠している?」
そして手に取って、光にかざした瞬間、見えてしまうのです。
薄くただよう、白いもや。
細い糸のような影。
あるいは、虹色にひび割れた不穏な光。
それが カビ なのか、曇り なのか、バルサム切れ なのか、初めての人には区別がつきません。
でも、知らないまま買ってしまうと、帰り道にだんだん不安が育ちます。
「これ……他のレンズに移ったりしないよな……?」
その心配、わかります。
人は“正体の見えないもの”を必要以上に怖がります。
ホラー映画の怪物は、姿を見せないときが一番怖いのと同じです。
しかし、心配しすぎる必要もありません。
カビはレンズの妖怪ではありません。
夜中に勝手に隣のレンズへ歩いていくような 人格は持っていません。
単に、湿度と油分と環境の問題です。
ただ、それが“やっかい”なだけなのです。
私はこれまで、中古レンズを何十本も見て、買って、売って、直してきました。
「これは助かる」「これは詰んだ」その境目がだんだんわかってきました。
今日はその、境界線の話 をします。
怖がらずに、しかし油断せずに。
レンズと付き合っていくための、ちょっとした手がかりを。
この記事でわかること
・カビ・曇り・バルサム切れの 見た目の違い
・ズームが勝手に伸びる「ズーム抜け」の正体
・修繕にいくらかかるのか 現実的な相場
・カビは「移る」と言われる理由と、実際の防ぎ方
・中古店やフリマで 3分でできるチェック方法
※この記事は、実際の観察と経験に基づきつつも、症状や状況は個体差があるため断定はできません。感じ方や判断は人それぞれです。本記事はあくまで参考としてお読みください。少しでも「怖くないレンズ選び」ができる手助けになれば幸いです。

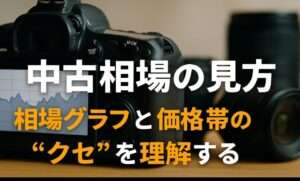
レンズのカビは“移る”のか
レンズにカビが生えていたと聞くと、人はすこし過剰な想像をします。
夜中に、レンズの中から胞子たちが行列をなし、棚の隣に並ぶレンズへと、そっと歩いていくような姿です。
まるで「カビ」という言葉そのものが、妖怪の名前であるかのようです。
けれど実際には、カビはそんなにドラマチックではありません。
湿度と温度、そしてレンズ表面に残った微細な皮脂や汚れ。
そういった “条件が揃った場所” に、静かに増えるだけです。
つまり「移る」というよりも、
「同じ環境なら、同じように生える可能性がある」
というほうが、ずっと現実に近いのです。
私が中古レンズを集め始めたころ、ひとつだけ大きな誤解をしていました。
「カビが生えたレンズと、他のレンズを同じ棚に置いたら即アウト」だと。
しかし実際は、そう単純ではありません。
湿度が低く、レンズをきちんと乾かし、皮脂や汚れを残さずに保管している環境では、
カビは “そもそも増殖しにくい” のです。
逆に、湿気の高い部屋や閉じっぱなしの防湿庫(内部が湿ったままの状態)は、
カビにとっては温室のようなものです。
だから、レンズのカビは 環境が招くもの と考えたほうが近いのです。
「梅雨どきに、クローゼットの奥に入れっぱなしの革靴だけ、なぜか白く曇ったことがある」
そうした経験がある人は、あの感覚を思い出すと近いです。
革靴が他の靴に “歩いて移った” わけではありません。
ただ、湿度が味方をしただけです。
では、実務としてどうすればいいのか。
・湿度は 40〜50% をひとつの目安にする
・撮影から戻ったら、一度 空気に触れさせる時間 を置く
・皮脂がついた前玉は、やさしくクリーナーで拭いておく
・カビが生えているレンズは、一旦は別の保管箱に分ける
この程度で、ほとんどの場合、十分です。
“レンズは生き物だ” と言う人がいますが、それは比喩の話であって、
手をかけすぎる必要はありません。
大切なのは、恐れすぎないことと、油断しないこと。
その真ん中です。
まとめ
・カビは レンズからレンズへ歩いて移動はしない
・ただし 高湿度 × 汚れ × 放置 の環境では複数のレンズに“同時多発”しやすい
・つまり 環境管理が本体
・カビ個体は念のため 別保管、湿度を整えれば十分に予防できる
カビ・曇り・バルサム切れの見分け方
じっと目を凝らし、光を送り、反射の中から“何か”を読み取ろうとする。
ただ、その“何か”が、カビなのか、曇りなのか、あるいはバルサム切れなのかで、レンズの未来がまったく変わるのです。
まず、深呼吸をします。
焦ってはいけません。
レンズは逃げません。
机に小さなライトを置き、部屋を少し暗くします。
このとき使うライトは、明るすぎないほうがいい。
強い光は、細かい影を消してしまうからです。
ペンライトを、レンズの正面からではなく、斜めから 当てます。
すると、そこに “世界” が現れます。
「ペンライトなんてない」という人へ。
糸のような影 ― それは「カビ」の可能性がある
糸がほぐれたような、細い線が複雑に絡んでいる。
あるいは、小さな白い綿毛が、ガラスのどこかにひっそりと座っている。
それらは、清掃で「ふっ」と消えることはほとんどありません。
カビは、見た目にかすかなやさしさを持っているのに、
写りにははっきりと影を落とします。
逆光の場面で、コントラストがすこし“溶ける”。
光の輪郭がにじんでしまう。
写真は、光でできているものですから、
光を邪魔されると、写真もまた、ほんの少し迷子になります。
面でふわりと光る ― それは「曇り」かもしれない
レンズを回しても、場所を変えても、いつも全体が白っぽい。
霧がうっすらガラスに張りついたように見える。
それが 曇り と呼ばれる状態です。
原因はひとつではありません。
コーティングの経年変化かもしれないし、微細な油分が広がっているのかもしれない。
「曇り」はカビよりも“静か”ですが、そのぶん、写りへの影響は 大きいことが多い のです。
写真が眠くなる。
空気がぼやける。
ピントが合っているのに、どこか合っていないように見える。
そういうときは、だいたい、曇りです。
角度を変えたとき、虹色の“島”が浮かぶ ― それは「バルサム切れ」の可能性が高い
レンズの中には、ガラスが何枚も貼り合わせられている部分があります。
その接着層が、年数とともに疲れてくると、
境界が島のように浮かび上がります。
光を当て、そっと角度を変えると、
まるで湖面に陽が反射するように、虹色の光がちらりと走る。
これが バルサム切れ と呼ばれるものです。
こればかりは、清掃では直りません。
貼り合わせを分離し、もう一度接着し直すという、職人の手作業の領域になります。
したがって、修繕費用は高くなりがちです。
「このレンズはまだ戦えるのか」
判断の分岐点は、ここにあります。
| 項目 | 見た目の特徴 | 推定される原因 | 写りへの影響 | 修繕難度 | 費用の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| カビ | 糸状・綿毛状・斑点状。斜め光で立体的に見えることが多い | 湿度・皮脂・保管環境の影響と考えられる | 逆光でコントラストが落ちやすい。白っぽいフレアが増えることもある | 中 | 分解清掃が前提になりやすく、1〜2万円台が起点になりやすい |
| 曇り(ヘイズ) | 面でふわっと霞がかる。位置を変えても全体的に薄く白い | コーティングの経年変化、油分の広がりなどが要因と推測される | 写真全体が眠い。シャープさが落ちることが多い | 中〜高 | 分解清掃でも改善に限界がある場合があり、1.5〜3万円帯になることがある |
| バルサム切れ | 光を当てて角度を変えると、境界に虹色の“島”が見える | 貼り合わせ層の劣化によると考えられる | コントラスト低下や光量ロス。進行すると実用性が下がる | 高 | 貼り合わせ再施工が必要なため数万円規模になりやすい |
| コーティング劣化 | 表面の艶がなく、ムラ状・くすみ状に見える | 長期使用や清掃による摩耗の蓄積と推測される | 逆光耐性の低下。色乗りが弱くなることがある | 中〜高 | 改善が難しい場合があり、基本的に買い替え判断も視野 |
| 内部チリ・気泡 | 点状で“止まっている”ように見える。斜め光で確認しやすい | 製造由来や経年混入。必ずしも不良ではない | 高絞りや強逆光で稀に写ることはあるが、影響は小さい | 低 | 清掃またはそのまま使用で問題ないことが多い |
現場での見分けの最短ルール
・光は 必ず斜め から当てる
・「糸」= カビ
・「面」= 曇り
・「島」= バルサム
・迷ったら 写真に撮って比較する
ズーム抜けは二種類あった
レンズというものは、見た目よりずっと内側が複雑です。
外からは、ただの筒にガラスが詰まっているだけのように見えますが、その実、内部には細かなカム機構やリング状のレールが通っていて、まるでミニチュアの観覧車のように動きながら焦点距離を変えています。
そして、この内部の“動き”がうまくいかなくなると、あの現象が起きます。
そう、
ズームが勝手に伸びる。
撮影の途中で、レンズが下へ向いた瞬間に、
スルスルと自重で伸びていく。
これを、一般に ズームクリープ と呼びます。
その1:勝手に伸びる「ズームクリープ」
ズームクリープが起きるとき、レンズは別に反抗しているわけではありません。
長年の使用で、ズームを動かすためのグリースが薄れたり、部品がなじみすぎて摩擦が減ったりしている状態です。
言ってしまえば、「ちょっと歳を重ねた」だけです。
「うちのレンズが年齢を感じてきたな」と、静かに受け止める人もいます。
逆に「絶対に許せん、直したい」という人もいます。
しかしこの現象、致命的ではありません。
ズームロックがついているレンズなら、それを使えばよい。
ついていないレンズなら、レンズバンド や、輪ゴム で軽く固定するという、なんとも原始的な対処で十分です。
その2:ズームでピントが抜ける「ピント抜け」
こちらは、ちょっと意味が違います。
ズームすると、ピントが 勝手にずれる。
これは壊れているわけではなく、レンズ設計の性質 であることが多いです。
ズームしながらピント位置が変わらないレンズを “パラフォーカル”。
ズームするたびピント位置が変わるレンズを “バリフォーカル”。
世の中のレンズは、ほとんどが後者です。
つまり、
「ズームしたらピントが抜ける」は、むしろ普通。
「なんだそれ」と思うかもしれませんが、
ピントは合わせ直せばいいだけです。
ミラーレスなら、AFをワンタッチで再駆動すれば終わります。
マニュアルフォーカスなら、拡大表示で合わせ直せば済みます。
ズームのたびにピントを合わせる。
それは、呼吸のたびにまばたきをするようなものです。
自然な動作として受け入れてしまえば、難しいことはありません。
まとめ
・勝手に伸びる → ズームクリープ
・ズームでピントが動く → ピント抜け(設計上普通)
・クリープは 輪ゴム で止められる
・ピント抜けは 撮影時に合わせ直すだけ
レンズは、あなたをいじめたいわけではありません。
ただ、そういうふうに作られているだけです。
修繕費の相場と「修る/買い替える」の境目
レンズを前にして悩むとき、人はだいたい静かになります。
財布を開くとき、人はもっと静かになります。
レンズの修繕費用は、一言で言えば 「思っているよりは高く、思っているほど絶望的ではない」 という位置にあります。
ここからは、できるだけ具体的に、しかし不安をあおらず、現実的なラインを見ていきます。
まず、分解清掃は「1〜2万円台」が土台になる
レンズの内部にカビや曇りがあると、外から拭いただけでは改善しません。
分解して、ガラスを一枚ずつ清掃する必要があります。
この「分解清掃」は、だいたい 1〜2万円台 から始まることが多いです。
「思ったより高いな」と感じる人もいますが、
レンズは精密機械です。
小さなガラスの板が何枚も並び、角度・距離・厚みがすべて揃っていなければ、写真は破綻します。
つまり、
分解清掃とは「元に戻す技術」です。
技術には、当然、代金が乗ります。
ズーム機構の修理は「数万円」になることがある
ズームリングの引っかかりや、内部の摩耗によるガタつきが発生している場合。
あるいは「ズームクリープを根本的に直したい」と思った場合。
ここから先は 構造部品の交換 が入る可能性があります。
そうなると、修理費用は 3〜4万円台 に伸びやすいです。
もちろんこれは、レンズの種類、部品の在庫、工房の工法によって変わりますので、
あくまで “目安” です。
バルサム切れは「直す」というより「手を入れ直す」
バルサム切れは、貼り合わせ部分の再施工が必要になります。
これは、レンズにとって 外科手術 のようなものです。
費用は、数万円台が一般的です。
さらに、納期も、他の修理より長くなりやすいです。
「それでも使いたいレンズかどうか」
ここが、判断のいちばん大きな分岐になります。
修理か、買い替えか — 判断のシンプルな基準
レンズの修理判断には、4つの軸があります。
・中古相場(同じレンズの“健康な個体”はいくらで買えるか)
・保守年限(メーカーがまだ部品を持っているか)
・代替性(同じ写りを、他で代替できるか)
・感情価値(そのレンズに思い入れがあるか)
この4つを、静かに見比べてください。
もし、健康な中古が修理費より安ければ、
買い替えたほうが合理的 です。
もし、似た写りのレンズがない、あるいはそのレンズで撮りたい理由があるなら、
修る意味はあります。
「直すか、買うか」というのは、
結局のところ、そのレンズがあなたにとって“道具”か“伴走者”か の違いなのです。
どちらでもいい。
ただ、見えている目で選べば、それでいい。
予防と保管の設計図
レンズの不調は、突然やってくるように思われがちです。
しかし実際は、「静かにつくられている」ことが多いです。
湿度が高い部屋に置きっぱなしにした数日。
撮影後に、レンズ表面の油分をそのままにしたままの数回。
防湿庫に入れたつもりが、内部が湿ったままで通気が止まっていた数時間。
そういった“小さな積み重ね”が、
いつの間にか、レンズ内部の環境を変えてしまいます。
カビは、人格を持っていない。
歩かないし、襲ってこない。
けれど、黙って条件を待っている のです。
だから、予防は「気合い」ではありません。
環境を、淡々と整えること です。
湿度は「40〜50%」がひとつの目安になる

湿度が高いとカビは増えやすい。
これはレンズに限らず、革靴、木製家具、教科書の端っこ、だいたいそうです。
防湿庫があるなら、それを 40〜50% にセットする。
乾燥剤を使うなら、湿度計を一緒に入れておく。
ここで大事なのは、
「管理しているつもり」
の状態が、一番危ないということです。
防湿庫に入れたから安心、ではありません。
中の湿気が飛んでいなければ、高湿度の箱になるだけ です。
つまり、防湿庫は「入れる前に、一度乾かす」が本体です。
撮影から帰ったら、
レンズのキャップを外し、空気に触れさせ、
ほんの数時間だけ、乾いた部屋に置いておく。
それだけで、レンズの未来はかなり変わります。
レンズは「動かす」ことで生きる
長いあいだ動かさないレンズは、
内部のグリスがゆっくりと固まりはじめます。
これは、レンズが「ふてくされている」わけではありません。
ただ、そういう構造なのです。
週に一度でいい。
ズームを一往復。
フォーカスリングをぐるり。
絞り羽根をひらいて、また閉じる。
たったそれだけで、レンズは「生きている状態」を保ちます。
靴も、着物も、レンズも、“動かすほど長持ちする”のはおもしろいですね。
そして、人は「忘れる」ので、ルールは少なくする
・撮影後は 一回、空気にあてる
・しまう前に 軽く前玉を拭く
・湿度を 40〜50% に保つ
・週に一度 動かす
これ以上は、いりません。
カビは恐怖ではなく、ただの現象です。
ただ、その現象は、気づかないうちに進むことがある。
だから、
“今できる最小の習慣” だけを持てばいい。
さいごに
レンズは道具です。
でも、人は時々、道具に心を映します。
「このレンズで撮った写真が好きだった」
「このレンズは、あの日の光を覚えている」
そういう気持ちが生まれてしまうから、
レンズはただのガラスと金属ではいられません。
だからこそ、見分けること。
知ること。
怖がりすぎないこと。
必要なら、手を入れること。
それだけで十分です。
レンズは、あなたを裏切りません。
ただ、環境の影響を受けるだけです。
どうか、ゆっくりと、息の合う関係でいられますように。
本記事の参照情報(出典整理)
※本記事の作成にあたり、下記の公式情報・メーカーガイド・実務系メンテナンス資料・利用者向け解説を参照しています。
内容・料金・対応可否は、製品状態・在庫・工房ごとの工法により変動しますので、最終判断は必ず現物確認と正式見積をご確認ください。
メーカー公式ガイド / メンテナンス情報
キヤノン(Canon)
レンズのお手入れ・湿気対策
https://personal.canon.jp/articles/tips/howto/camera4
キヤノン
セルフメンテナンスの基本
https://canon.jp/support/repair-index/after-support/maintenance/self
キヤノン FAQ
結露時の取り扱い・オーバーホール相談
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/103299/
ニコンイメージングジャパン
レンズのお手入れガイド
https://nij.nikon.com/enjoy/phototech/lenslesson/lesson10.html
ニコンイメージングジャパン
後群・前群の清掃と扱いの注意
https://nij.nikon.com/enjoy/phototech/lenslesson/lesson13.html
ニコン サポート
レンズ内部ゴミ・カビの判断指針
https://nij.nikon.com/support/faq/products/article?articleNo=000060238
タムロン(TAMRON)
修理料金目安表
https://www.tamron.com/jp/consumer/repair/price.html
タムロン
ズームロック・機構解説
https://www.tamron.com/jp/consumer/technology/mechanism/
販売店・専門店によるメンテナンス案内
カメラのキタムラ
店頭メンテナンスサービス
https://www.kitamura.jp/service/maintenance/
フジヤカメラ
清掃・分解整備の費用目安
https://www.fujiya-camera.co.jp/blog/detail/info/20210718/
フジヤカメラ
整備費用に関する考え方と留意点
https://www.fujiya-camera.co.jp/shop/e/ec-22123a/
独立系修理工房(費用例・工法の参考)
Old Lens Repair Studio
分解再組立・カビ取り・ヘリコイド清掃などの料金例
https://oldlens-repair-studio.com/price/
横浜カメラサービス(例:分解清掃の参考価格帯として)
https://yokohama-camera-service.com/
ユーザー実例(修理プロセスの流れ確認用)
note:ズーム機構修理の見積・実施例
https://note.com/takahiro_mono/n/n2dba479786e2
運用・対策関連
レンズクリープ対策用 レンズバンド
https://www.amazon.co.jp/dp/B0075FPN6Y
湿度管理(防湿庫+湿度計 運用例)
https://shodensha-inc.co.jp/