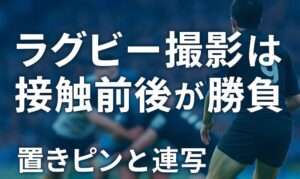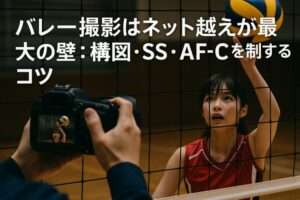子どもの初めての運動会を撮影する日は、保護者にとって特別な一日です。
しかし、いざカメラを調べてみても、
どの機種を選べばいいのか迷う方が多いのではないでしょうか。
以前の記事**「運動会や発表会におすすめのカメラメーカーは?保護者が迷わないブランド選び」**では、ブランドごとの特徴や選び方を詳しくまとめました。
そこで今回はその続編として、
2025年9月21日時点で最新モデルとして確認された具体的なカメラと望遠レンズを、実名で紹介していきます。
 バテ男
バテ男カメラを始めよう!と思っても、種類が多すぎて・・
最初はブランドの評判だけで選んで失敗した経験がある方も多いのではないでしょうか。



私はまさにそれでした・・
なんだかよくわからない機能が多すぎて結局スマホで撮影に__



どの機種が実際に運動会で使いやすいのか、もっと具体的な情報が欲しいですよね
そこで今回はその続編として、
2025年9月21日時点で最新モデルとして確認された具体的なカメラと望遠レンズを紹介していきます。



実際に使える!と評判のカメラとレンズを見ていきましょう!
この記事を読めば、最新モデルの中から自分に合った一台を見つけるための具体的なヒントが得られるかもしれませんので、ぜひ最後までご覧ください
この記事でわかること
- 2026/01/21時点で最新の運動会向けおすすめカメラ
- 初心者保護者でも扱いやすい望遠レンズの型番と特徴
- 運動会当日に活用できる撮影Tips


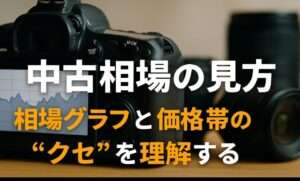
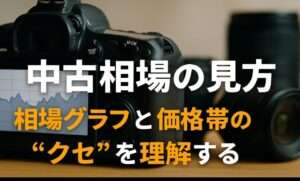


初心者保護者向け:2025年おすすめミラーレス一眼【具体モデル比較】
初めての運動会
うまく撮影できるか心配ですよね・・・
大切なお子さんが一生懸命練習して臨む本番、保護者の皆様の緊張もひとしおでしょう。
せっかくだからとカメラをのぞいてみても、初めて目にする用語や性能ばかり・・・
購入にあたっては、
「設定をいじる余裕なんてないかもしれない」と不安に思う人もいれば、
「せっかく買うなら長く使いたい」と考える人もいるでしょう。



せっかくカメラを買っても、最初はオート撮影で精一杯という方は多いと思います



それ、私です・・
考えるよりパシャパシャ撮っちゃえ!って感じで・・
けれど撮影に慣れてくると、
もう少し自由に表現したくなる瞬間が
必ず訪れます



だからこそ、最初はオート任せで確実に写しながら、後々は一歩進んだ撮影にも挑戦できる機種を選ぶのが大切です。
ここでは2025年9月21日時点で確認できる最新モデルを、
初心者から将来本格派を目指す人まで成長に合わせて選べるようレベル別に整理しました。
エントリーモデルとしているカメラであっても、その軽さや連写性能を理由にプロが取材現場でサブ機として活用する例も少なくありません。
初めての運動会を確実に撮るだけでなく、家族の成長を長く撮り続ける相棒としても頼れる機種たちです。
手堅く始めたい方向けエントリーモデル
最初の一台に求めるものは、迷わず撮れる安心感と、成長しても手放さずに使える実力です。



ここで紹介する2機種はまさにその両方を兼ね備えています。
Canon EOS R50
24.2MP APS-Cセンサーを搭載した軽量ボディは、初めて一眼を手にする保護者でも片手で扱えるほどコンパクト。
「シーンインテリジェントオート」は人物や動きを自動判別し、光や色を即座に最適化します。
競技中に設定をいじる余裕がなくても、ボタン一つで撮影環境に合った結果が得られます。
被写体検出AFは顔や目を自動で追従。
スタート直後に一気に駆け出す子どもの表情を、オートのまましっかり捉えてくれます。
さらにR50は“エントリー機”と位置付けられていながら、その軽さと最大15コマ/秒の高速連写性能から、
プロカメラマンが取材現場機として携行することも珍しくありません。
例えばスポーツ誌のフォトグラファーがメイン機を望遠撮影に回し、ゴール後の選手の笑顔を近距離で狙う際に、軽快なR50を肩から下げてすぐに構える――そんな使い方が実際に行われています。



軽くて操作もシンプル。これなら初めてでも肩がこりませんね。



プロが現場でも使うようなカメラなら、長く安心して使えそうです。



ええ。
長期にわたって頼れる一台と考えて良いでしょう。
Nikon Z50 II
2024年末に登場したエントリーモデル。
オートモードでは顔や動きを自動で認識し、明るさや色を瞬時に調整します。
さらに「Pre-Release Capture」をオンにしておけば、シャッター半押しの段階から記録を開始。
押したつもりが遅れた――という失敗を防ぎ、スタートダッシュの一瞬も確実に残せます。
バッテリー持ちも良好で、朝から夕方まで続く運動会でも心配なし。
そしてこのZ50 IIも、報道現場やスポーツ取材でプロが使うカメラとして知られています。
例えば新聞社のカメラマンが大口径望遠を構える一方で、観客席や表彰式をすばやく撮るためにZ50 IIを肩に下げておく――その軽快さと高画質がプロに評価されているのです。



初心者向けと聞いていたけど、プロも使うんですね。



そう。エントリーモデルは“初心者専用”ではなく、現場でも通用する確かな性能を備えています。
この2機種は、**「最初は完全オートで失敗なく撮りたい」**という保護者に安心を与えながら、将来はステップアップした撮影にも応えてくれる懐の深さを持っています。
初めての運動会を確実に残すだけでなく、その後の家族の成長記録にも長く付き合える――
まさに“手堅く始めたい人の最初の一台”にふさわしい選択肢です。
中級〜将来拡張モデル
オートに任せてまずは撮りたい。
でも数年後には自分の意図で設定を変え、より表現を広げていきたい――
そんな保護者に向くのがこのクラスです。
エントリー機より一歩進んだ操作系と、交換レンズやアクセサリーの選択肢が豊富。
成長に合わせて撮影スタイルを深めても無駄になりません。
Sony α6700
AI被写体認識が優秀で、オートモードでも子どもの動きを即座に捉えます。
同時に、細かくAFエリアを設定したり、高速連写やRAW現像など中級者が挑戦したくなる要素も充実。
豊富なEマウントレンズを活用すれば、望遠・ポートレート・夜景など幅広い撮影ジャンルにステップアップできます。
※Eマウントは対応レンズが多く、後から撮影の幅を広げやすい規格です。


FUJIFILM X-S20 / X-T50
フィルムシミュレーションにより、オート撮影でも雰囲気ある色味を再現。
初心者でもすぐにスマホでは撮影が難しい“絵になる写真”が得られます。
さらに、マニュアル露出やフィルムシミュレーションの細かい調整など表現を追求したくなった時にも応えられる操作系を備えています。
深層学習ベースの被写体検出AFは素早く動く子どもを自動追従。
家族写真を柔らかく仕上げたい方から、自分の作品作りに挑戦したい方まで幅広く支持されています。



フィルムシミュレーションなら最初はオートでも、慣れたら表現を広げられますね。



X–T50のような、ダイヤルでシミュレーション変更できるタイプだとより便利にさまざまなシチュエーションで撮影が可能ですね!
連写と先取り重視の上位モデル
運動会を何度か経験すると、
「ゴールの瞬間を一枚も逃したくない」
「夕方の薄暗い光でもきれいに撮りたい」
といった願いが強くなります。
こうした一瞬の勝負や厳しい条件に対応したい人に向くのが、この“上位モデル”のクラスです。
連写速度や先取り撮影、暗所での画質、ボディの堅牢性など、エントリー機を明らかに上回る性能が備わっています。
Panasonic LUMIX G9 II
AFC 60fpsのブラックアウトフリー連写を搭載。
プリ連写機能をオンにしておけば、シャッターを押す少し前から画像を記録してくれます。
例えばリレーのバトン渡し。
子どもが腕を伸ばす一瞬前から連写が始まるので、
渡した瞬間の表情を逃さず残せます。
マイクロフォーサーズ規格のため望遠レンズでも軽量。
長時間グラウンドを歩き回っても腕が疲れにくく、長丁場の運動会でも頼れる存在です。
OM SYSTEM OM-1 Mark II
最大120fpsのPro Captureで動き始めを先取り。
これは、シャッターを半押ししているときから記録が開始され、子どもがスタートラインで
わずかに体を傾けた瞬間からシャッターを押した後まで一連の動きを記録できる機能です。
究極の瞬間をとらえるプロキャプチャー 120コマ/秒 連写
シャッターボタン半押しで記録を開始、シャッターボタン全押しの瞬間からさかのぼって記録することで、人の反応タイムラグ、カメラの動作タイムラグが原因で撮り逃がした瞬間も確実にとらえるプロキャプチャー。最高120コマ/秒 (AF/AE固定) の高速連写で被写体の素早い動きの瞬間をとらえることができます。まさにスローモーション動画から瞬間を切り出すということが可能になります。さかのぼって撮影できるコマ数は、最大70コマです。
参照:OM-1 製品特徴 公式HP
AF/AE追従で50コマ/秒の撮影も可能です。
さらに強力な防塵防滴性能を備え、突然の小雨や砂埃が舞うグラウンドでも安心。
プロの撮影現場で求められる耐久性が、家族の思い出を守る場面でも大きな安心につながります。
オートモードでも鮮明な仕上がりを実現し、設定が分からなくても失敗が少ないのも魅力です。
Nikon Z6 III
フルサイズセンサーを搭載し、暗い夕方や体育館でもノイズを抑えて撮影可能。
Pre-Release Captureと9種の被写体検出AFで、屋外屋内を問わず動きの速いシーンを的確に捉えます。
例えば学芸会など室内の舞台。暗い照明下でも子どもの表情を鮮明に写し、背景を大きくぼかして主役だけを際立たせることができます。
オートモードを備えているので、初めてでも安心。
その一方で、RAW現像やマニュアル撮影など将来的に本格的な作品づくりへ挑戦したくなった時にも十分に応えてくれるスペックを持っています。



初めはオートで十分。けれど撮影に慣れてきたら、こうした上位機の性能が一歩先の表現に連れて行ってくれます。



プロの現場でも使われる機能が、家族の思い出作りにそのまま活きるのは心強いですね。
オートで確実に撮りたい今から、将来は自分の手で表現を広げていきたい人まで。
成長の段階に合わせて選べる機種をレベルごとに整理しました。
中でもエントリーと呼ばれるカメラは、単なる入門機ではありません。
その軽快さと信頼性を理由に、現場のプロが取材やイベントでサブ機として持ち出すことも珍しくないのです。
初めての運動会を確実に残したい保護者にとっても、家族の記録を長く続ける一台としても、末永く頼れる存在になるでしょう。
運動会に最適な望遠レンズ【具体モデル比較】
運動会では、想像以上に子どもとの距離が離れます。
徒競走のゴールや遠くの演技ステージを、標準レンズ一本で大きく切り取るのは難しいものです。



僕も最初は標準ズームで挑んで、わが子が豆粒みたいにしか写りませんでした。



私も同じです。近くに見えても、写真にすると意外と遠いんですよね。



だからこそ、望遠ズームは必須という声も多いのです。
ここでは 「初心者が扱いやすい軽量レンズ」 を中心に、運動会撮影に強いモデルを紹介します。
APS-C用 軽量望遠ズーム
Canon RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM
換算約88-336mmの焦点域をカバーし、初めての望遠に最適。
IS(手ブレ補正)搭載で、手持ち撮影でもブレをしっかり抑えます。
例えば徒競走でゴールテープを切る瞬間、遠くからでも表情を大きく捉えられます。
Nikon Z DX 50-250mm F4.5-6.3 VR
換算約75-375mmをカバー。
わずか約405gという軽さながら、VR(手ブレ補正)を備え、走る子どもを安心して狙えます。
リレーの奥レーンなど、肉眼では遠く感じる場面でも、子どもの表情を鮮明に切り取れます。
バッテリー持ちの良いZ50 IIとの相性も抜群で、朝から夕方までの運動会をカバーできます。
Sony E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS
換算約105-525mmという長めの焦点距離を軽量ボディで実現。
広いグラウンドの一番奥のレーンまで確実に捉える力があります。
Gレンズならではの高い解像力と色再現も魅力で、
望遠でも背景を大きくぼかし、子どもを際立たせた写真が撮れます。
FUJIFILM XF70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR
換算約105-450mm。
防塵防滴設計に加え、OIS(光学手ブレ補正)を搭載。
砂埃が舞うグラウンドや突然の小雨でも安心して撮影できます。



家族写真を柔らかい色で残したい方にも人気が高く、運動会後のポートレートにも活躍します。



天気が怪しくても心配いらないのは助かりますね。
マイクロフォーサーズ用
OM SYSTEM M.Zuiko Digital ED 40-150mm F4 PRO
換算80-300mm相当。
IP53相当の防塵防滴仕様で、風が強い運動場や砂埃の舞う環境でも安心。
軽量かつ高い解像力を持ち、長時間の手持ち撮影でも疲れにくい設計です。
例えば組体操のように長時間同じ場所で撮影するシーンでも、疲れにくさが大きなメリットになります。



どのレンズも「遠くの子どもの一瞬の笑顔を大きく残したい」という保護者の願いに応えてくれます。



標準レンズでは届かない距離でも、望遠なら決定的瞬間を逃さず撮れますね。
望遠レンズを選ぶときは、カメラ本体との重量バランスを意識するのがポイントです。
軽量ボディに重いレンズを付けると、長時間の手持ち撮影で腕が疲れやすくなります。
自分の体力や撮影スタイルに合わせて、
**「持って歩いても疲れにくいか」**を実際に店頭で試すことが、失敗を防ぐ一番の近道です。



カメラやレンズをレンタルしている店もあるみたいですので、
購入前に実際に手に取って試してみてもいいかもしれませんね
フルサイズ機ユーザーにおすすめの望遠レンズ
運動会や発表会をフルサイズ機で撮る理由は、暗いシーンに強い高感度性能と背景を大きくぼかせる表現力にあります。



フルサイズなら体育館でもノイズを抑えやすいですよね。



そう聞くと魅力的ですが、レンズは何を選べばいいのでしょう。



そこがポイント。
ボディの性能を生かすには、対応する望遠レンズが必要です。
ここでは、フルサイズ機と組み合わせて初めてその強みを発揮する代表的な望遠ズームを紹介します。
Nikonユーザー向け
NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
Z6 IIIなどのZフルサイズボディに最適。
100mmから400mmまで幅広くカバーし、広いグラウンドの奥のレーンまで鮮明に捉えます。
手ブレ補正(VR)を内蔵しているため、夕方の競技や体育館のステージでも安心。
S-Lineならではの高い描写力で、背景を柔らかくぼかしつつ、
子どもの表情をくっきりと浮かび上がらせます。
Canonユーザー向け
Canon RF 100-400mm F5.6-8 IS USM
EOS Rシリーズのフルサイズ機に対応。
軽量ながら400mmまでの焦点域をカバーし、
運動会や発表会の奥のシーンをしっかり写し出します。
IS(手ブレ補正)と高速AFを搭載し、動きの速い子どもを鮮明に捉えやすいのが特長です。
B フルサイズでもこの軽さなら持ち運びやすそうですね。
Sonyユーザー向け
Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II
α7シリーズなどフルサイズEマウント用の大定番。
F2.8通しの明るさにより、背景を大きくぼかしたドラマチックな一枚を撮影できます。
体育館や夕方の競技など、光量が少ない場面でもシャッター速度を稼ぎやすく、ブレを抑えて撮影可能。



プロも多く使うレンズで、発表会や舞台でも頼りになりますよ。
フルサイズ望遠レンズ選びのポイント
フルサイズ機と望遠レンズの組み合わせは、APS-Cやマイクロフォーサーズより重量と価格が一段上になります。
そのぶん、暗所での画質や背景ボケの美しさは圧倒的。
例えば夕暮れのリレーや照明の少ない学芸会など、
他の規格では難しいシーンも、フルサイズならノイズを抑えつつ
主役だけをふわりと浮かび上がらせることが可能です。



機材は重くなりますが、
家族の一生に一度の舞台を本格的に残したい人には価値がありますね。



その通り。
大切な一瞬を最高の画質で残すなら、フルサイズ+望遠ズームという選択は十分に意味があります。
初心者保護者向けの実践的な組み合わせ例(まとめ表)
| 用途・特徴 | カメラ本体 | 推奨レンズ |
|---|---|---|
| 軽量で失敗しにくい定番 | Canon EOS R50 | RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM |
| スタートの瞬間を先取り | Nikon Z50 II | Z DX 50-250mm F4.5-6.3 VR |
| 奥レーンまで確実に捉える | Sony α6700 | E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS |
| 長時間でも疲れにくい軽量望遠 | Panasonic LUMIX G9 II または OM SYSTEM OM-1 Mark II | M.Zuiko Digital ED 40-150mm F4 PRO |
| 色再現を重視した家族写真派 | FUJIFILM X-S20 または X-T50 | XF70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR |
| 暗所・背景ボケ重視(フルサイズ) | Nikon Z6 III | NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S |
組み合わせごとのポイント一覧
- Canon EOS R50 + RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM
- シーンインテリジェントオートで被写体を自動判別。
- 軽量セットで一日持ち歩いても疲れにくい。
- Nikon Z50 II + Z DX 50-250mm F4.5-6.3 VR
- Pre-Release Captureで号砲の一瞬前から記録。
- 長時間撮影でもバッテリー持ちが良く安心。
- Sony α6700 + E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS
- 換算約525mmの超望遠で奥レーンまで確実に捉える。
- AI被写体認識で素早い動きを正確に追従。
- OM SYSTEM OM-1 Mark II + M.Zuiko Digital ED 40-150mm F4 PRO
- マイクロフォーサーズ規格で望遠でも圧倒的に軽量。
- Pro Captureで決定的瞬間を逃さない。
- FUJIFILM X-S20 または X-T50 + XF70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR
- フィルムシミュレーションで柔らかな色味を再現。
- 防塵防滴設計で砂埃の多い運動場でも安心。
- Nikon Z6 III + NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
- フルサイズならではの高感度性能で夕方や体育館でもノイズを抑える。
- 背景を大きくぼかして主役を際立たせる一枚が撮れる。
さいごに
初めての運動会撮影では、どんなカメラを選ぶかよりも、まず失敗を減らす準備が大切です。



僕は最初の年、カメラを持ってはいたけど設定に迷って、気づいたら競技が終わっていました。



私も。レンズ交換のタイミングをつかめなくて、ゴールシーンを撮りそこねたんです。



だからこそ、事前にボディとレンズを「このセット」と決めておくと安心ですよね。当日はそのまま構えるだけでいい。



そうですね。重さや握りやすさも、実際に店頭で触って確かめておくと当日の焦りが減ります。
この記事では、オートで気軽に撮りたい初心者から、数年後に本格的な表現に挑戦したい人まで、
成長に合わせて選べるカメラとレンズの具体的な組み合わせを紹介しました。
遠くのレーンをしっかり捉えたいのか、
暗い体育館でノイズを抑えたいのか――。
自分がどんな場面を多く撮るのかを具体的に思い描くことで、
選ぶべきセットは自然に絞れてきます。



私も次は、子どもの学芸会をきれいに残したいから、暗所に強いフルサイズを検討してみます。



いいですね。僕も次の年は、背景を大きくぼかしたくて望遠レンズを追加しました。一度撮影を経験すると、「次はこう撮りたい」という気持ちが出てくるんですよ。
カメラ選びはゴールではなく、
家族の記録を楽しむ長い旅の始まりです。
撮影した後は、クラウド共有やフォトブック作成など、思い出を形に残す楽しみも広がります。
今回のモデル比較を参考に、
撮影スタイルに合った一台を見つけて、大切な一瞬をあなたらしい形で残せることを祈っています。
- [運動会や発表会に強いメーカーは?保護者が迷わないカメラブランド選び]
初めての一眼選びで迷う方へ、各メーカーの特徴と得意分野を整理しています。
「どのブランドが自分に合うか」から検討したい方はこちらへ。 - [発表会や体育館撮影で失敗しないためのレンズ選びと設定ガイド]
室内の暗い環境で子どもをきれいに撮るためのレンズ選びと具体的な設定のポイントを詳しく紹介。 - [家族写真をもっと素敵に残す!フォトブック作成とクラウド共有のコツ]
運動会で撮った写真を祖父母や親戚と共有するためのフォトブック作成法やクラウドサービス活用法を解説しています。 - [運動会撮影を成功させるために前日までに必ず準備すべきチェックリスト]
予備バッテリーから天候対策まで、当日あわてないための具体的な準備項目を一覧化しています。
参考HP:マップカメラ、カメラのキタムラ、フジヤカメラ、価格.com 、 J-カメラ、カメラファン、aucfan
※本記事は各社公式資料・製品ページなど一次情報をもとに執筆しています。
機能や仕様はファームウェアの更新などで変更される可能性がありますので、最新情報は必ず公式サイトで確認してください。
参照サイト一覧
メーカー公式製品情報・マニュアル
- Canon U.S.A. – EOS R50 / R10 / RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM / RF 100-400mm F5.6-8 IS USM 製品ページ
- Nikon Imaging Japan / Nikon USA – Z50 II / Z6 III / NIKKOR Z DX 50-250mm F4.5-6.3 VR / NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S 製品ページ・オンラインマニュアル
- Sony Electronics / Help Guide – α6700 / E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS / FE 70-200mm F2.8 GM OSS II 製品ページ・Anti-Flicker/可変シャッター ヘルプガイド
- FUJIFILM Xシリーズ公式 – X-S20 / X-T50 / XF70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR 製品仕様・フィルムシミュレーション解説ページ
- OM SYSTEM (OMデジタルソリューションズ) – OM-1 Mark II / M.Zuiko Digital ED 40-150mm F4 PRO / 運動会撮影テクニック特集
- Panasonic LUMIX公式 – LUMIX G9 II 製品ページ・ブラックアウトフリー連写 / プリ連写(Pre-burst)解説
撮影設定・公式解説