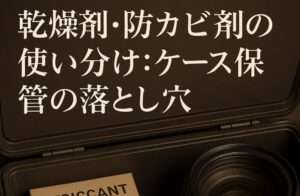夏の昼下がり。子どもの笑顔を撮ったはずなのに、画面を開くと顔が真っ黒。
背景の空だけがまぶしく光って、まるで影絵のようになっていた――
そんな経験、ありませんか?
私も何度もやらかしました。
運動会で、旅行先で、せっかくの笑顔が暗闇に沈んでしまう。
その瞬間、胸の奥がズンと重くなります。
「撮ったはずの“あの光景”が写ってない」――
その悔しさを、きっとあなたも感じたことがあると思います。
でも、あれは腕のせいではありません。
太陽が高く光が強すぎる炎天下では、カメラの自動露出がうまく働かないことが多いのです。
明るい背景に惑わされたカメラが、被写体の顔を暗くしてしまう。だからこそ、“自分で光を調整する”力が必要になります。
この記事では、逆光や炎天下の撮影で「顔が暗くなる」原因と、それを防ぐための露出補正とレンズフードの使い方を、実践的に解説します。
 バテ男
バテ男太陽を敵ではなく味方に変えるための考え方と操作手順を、私自身の失敗の積み重ねから学んだ形で整理しました。



ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。
この記事でわかること
・逆光や炎天下で顔が暗く写る理由
・プラス/マイナス補正の考え方と設定目安
・測光モードやヒストグラムの活用方法
・フードの正しい使い方と“過信”への注意
・被写体別(人物・風景・花)の撮影ワークフロー


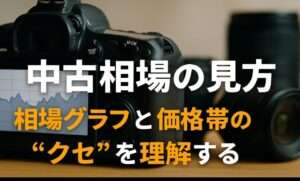
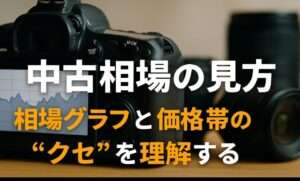
逆光・炎天下の撮影で何が起きているのか
カメラが「光にだまされる」仕組み
撮影中、ファインダーを覗いた瞬間に「思ったより暗い」と感じたことはありませんか。
それは、カメラが“正直すぎる”からです。
太陽のように強い光があると、カメラは画面全体の明るさを平均的に判断して「これくらいがちょうどいい」と決めます。
ところが、被写体の顔はその中で影の部分にあります。
背景が明るすぎると、カメラは「全体が明るい」と勘違いしてしまい、顔を暗く写してしまうのです。
いわば、カメラの目が太陽にだまされている状態です。
人間の目は柔軟で、瞬時に光を補正して「顔が暗い」と認識できます。
けれどカメラは、センサーが受けた光の量を“数値”として扱うため、背景の光に引っ張られて誤った判断をしてしまうのです。
炎天下がもたらす「明暗差の罠」
炎天下では、光のコントラストが極端になります。
たとえば、真夏の午後。
白いシャツと黒髪が同じフレームに入ると、白い部分は飛び、黒い部分は潰れてしまう。
これがいわゆる「白飛び」「黒つぶれ」と呼ばれる現象です。
カメラのセンサーは、明るいところと暗いところを同時に記録する力(ダイナミックレンジ)に限界があります。
そのため、どちらか一方に露出を合わせると、もう片方が犠牲になることがあるのです。
だからこそ、撮影者が補正値を判断して“意図的に”バランスを取る必要があります。
逆光で起こる「光の乱反射」
逆光では、別のトラブルも発生します。
太陽光がレンズの内部に入り込むことで、光が反射し合い、フレアやゴーストが発生します。
画面全体が白く霞んだり、光の輪が浮かび上がったりするのはこの現象が原因です。
このとき、被写体の輪郭がぼやけ、コントラストが低下してしまいます。
つまり、撮りたかった“立体感”や“空気の透明感”が失われてしまうのです。
フードを使えば、この不要な光を物理的に遮ることができます。
また、撮影者自身の立ち位置や構図を少し変えるだけでも、光の入り方が大きく変わることがあります。
光を制する最初の一歩
結局のところ、逆光や炎天下で露出が安定しない理由は「カメラ任せ」にあるのです。
露出補正で明るさを制御し、フードで余分な光を遮る。
この二つの組み合わせこそが、強い光に翻弄されないための最初の一歩になります。
どちらか一方だけでは不十分。
露出と遮光、数値と物理の両輪で光をコントロールすることが、安定した写りをつくる鍵なのです。
✅ まとめ
・カメラは明るい背景に引っ張られ、被写体を暗く写しやすい。
・炎天下では白飛び・黒つぶれが起きやすい。
・逆光ではフレアやゴーストが発生しやすく、画質が低下する。
・露出補正とフードの併用が、光を制御する最初のステップとなる。
逆光・炎天下対策5選_露出補正で“意図した明るさ”
カメラ任せでは「正しい明るさ」にならない
露出とは、カメラのセンサーにどれだけの光を取り込むかを決める仕組みです。
これは絞り・シャッタースピード・ISO感度の組み合わせで決まります。
カメラは自動的に「適正露出」を判断してくれますが、それはあくまで“平均値”。
つまり、被写体がどんな光の中にいるかまでは考えてくれません。
結果として、逆光では顔が暗く、炎天下では背景が飛んでしまう。
このとき必要なのが、露出補正です。
ダイナミックレンジという“限界”
どんなに性能の高いカメラでも、人の目ほど明暗を見分けることはできません。
人の目は、暗い室内から炎天下の屋外まで、瞬時に調整できます。
しかしカメラのセンサーが記録できる明暗の幅――これをダイナミックレンジといいます――には限界があります。
炎天下のように明暗差が大きい場面では、センサーが光を受け止めきれず、明るい部分は真っ白に、暗い部分は真っ黒に潰れてしまうのです。
露出補正とは、この“センサーの限界の中で、どの明るさを優先するか”を選ぶ操作でもあります。
たとえば、逆光で人物を明るく撮りたいならプラス補正をして、暗部(シャドウ)を優先的に持ち上げる。
反対に、炎天下で白い服や空の階調を守りたいなら、マイナス補正でハイライトを守る。
こうして“どこに光を残すか”を決めていくのが、露出補正の本質です。
プラス補正とマイナス補正の使い分け
露出補正とは、カメラが出した明るさの基準値を“意図的に”ずらすこと。
プラス補正では全体を明るく、マイナス補正では全体を暗くします。
たとえば逆光で顔が沈むなら+0.3〜+1.0段。
背景が明るすぎるときは−0.3〜−1.0段。
これを意識的にコントロールすることで、目で見た印象に近づけられます。
測光モードを使いこなす
露出補正の効果を最大限に引き出すには、測光モードの理解が欠かせません。
カメラがどこを基準に明るさを測るのかを決める設定です。
逆光では、被写体の顔など“主役”に露出を合わせたいので、スポット測光や中央重点測光を選びましょう。
背景が明るいままだと、カメラはそちらを優先してしまい、顔が暗くなりがちです。
この設定を変えるだけで、撮影結果が驚くほど安定します。
ヒストグラムで確認する癖をつける
撮影後は、画面のプレビューだけで判断せず、ヒストグラムを確認しましょう。
ヒストグラムは、明るさの分布を示すグラフです。
右端が白飛び、左端が黒つぶれを意味します。
もしグラフがどちらかに張り付いているなら、露出が偏っているサインです。
炎天下では白飛びを防ぐため、右端を少し残すように撮る。
逆光では、被写体の明るさがつぶれていないかを確認します。
この“確認の習慣”が、露出を安定させる近道です。
おまけ_NDフィルターの活用:強すぎる光を“弱める”最終手段
露出補正やダイナミックレンジ設定を使っても、どうしても光が強すぎる場面があります。
たとえば、真夏の砂浜や白いコンクリートの反射。
あるいは水面の照り返しが強い風景などです。
こうした状況では、カメラの設定だけでは光量を抑えきれず、
絞りをF11以上にしても白飛びすることがあります。
そこで役立つのが**NDフィルター(減光フィルター)**です。


「ND8」や「ND16」といった表記は、どれだけ光を減らすかの強度を示しています。
たとえばND8なら光を1/8に、ND16なら1/16に減らすことができます。
これにより、炎天下でも「絞りを開けてボケを生かす」撮影や、「長時間露光で水面をなめらかに写す」表現が可能になります。
NDフィルターを使うときは、露出補正とのバランスが重要です。
光を減らした分だけ、カメラが自動で明るくしようとするため、
マニュアル露出モードまたは固定露出補正を併用すると安定します。
また、NDフィルターを付けたままオートフォーカスが迷う場合があるので、
ピントを合わせてから装着するのも一つのコツです。
NDフィルターには可変タイプ(ND2〜ND400など)もあり、
ダイヤルを回すだけで光の量を調整できる便利なモデルもあります。
屋外イベントや日中のポートレートでは、
ND8〜ND16あたりが扱いやすく、画質劣化も少ないと言われています。
✅ NDフィルター活用のポイント
・炎天下や白い地面・水面の反射にはND8〜ND16を使用。
・被写体の明るさを維持しながら、背景の白飛びを防げる。
・マニュアル露出で使うと安定。オート任せだと補正が暴れる。
・濃度が高いNDほど、色ムラやAF誤作動に注意。
実践:炎天下・逆光の補正まとめ
| シーン・状況 | 推奨設定・行動 | 理由・目的 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 逆光で顔が暗いとき | +0.3〜+1.0段のプラス補正。測光はスポットまたは中央重点。 | 被写体の表情を明るくし、背景に惑わされない露出を得る。 | 背景が飛びやすい。ヒストグラム右端をチェック。 |
| 炎天下で白飛びしやすいとき | −0.3〜−1.0段のマイナス補正。ISOを最低値、シャッターを速く。 | ハイライトを守り、空や衣服の階調を保持する。 | 暗部が潰れやすい。RAW撮影で補正余地を確保。 |
| 明暗差が大きい(白い服+黒髪など) | 「どこを残したいか」を決める。人物重視なら+補正、背景重視なら−補正。 | ダイナミックレンジの限界内で“守るべき明るさ”を選択。 | 両方を無理に残そうとすると中間調が崩れる。 |
| ダイナミックレンジを最大化したいとき | カメラの「DR設定」をON(DR200〜400、ハイライト優先など)。RAW撮影を推奨。 | センサーが拾える明暗幅を広げ、補正ミスを救済。 | DRを上げるとISOが自動上昇する機種あり。ノイズに注意。 |
| どの補正値が最適かわからないとき | まず+0.3段で撮影。ヒストグラムを確認してから±方向に調整。 | 感覚ではなくグラフ基準で判断できる。 | 0.3段ずつ調整。いきなり1段以上動かさない。 |
| 白っぽくコントラストが低いとき | レンズフードを装着。光源が画角に入らないように立ち位置を変更。 | フレア・ゴーストを防ぎ、コントラストを回復させる。 | 直射が強い場合は手や帽子で補助遮光。 |
| 撮影後のチェック時 | ヒストグラムの右端・左端を確認。右端に張り付き=白飛び、左端=黒つぶれ。 | 露出バランスを客観的に把握できる。 | 液晶の明るさに惑わされない。グラフで判断。 |
| 迷ったときの最終判断 | 「被写体が見える方」を優先して補正。 | 暗部は潰れると復元困難。明部は後処理で戻しやすい。 | 露出補正=“どちらを救うか”の判断。 |
現場で迷わないために、以下の順番で操作してみましょう。
- 光の向きと強さを確認する。
- 測光モードを「スポット」または「中央重点」に設定。
- まず+0.3段で撮影し、暗ければさらに+へ。
- 背景が飛んでいれば、−側に補正して調整。
- 撮影後、ヒストグラムを確認して再調整。
この5ステップを繰り返すだけで、炎天下や逆光での“露出ブレ”は確実に減っていきます。
✅ まとめ
・ダイナミックレンジとは、センサーが記録できる明暗の範囲。
・逆光では暗部を救うためにプラス補正、炎天下ではハイライトを守るためにマイナス補正が有効。
・測光モードとヒストグラムを活用すれば、露出の安定度が大きく向上する。
・「光のどこを残したいか」を意識することが、補正の第一歩。
フードで守る画質:光の侵入を制御する
フードの基本役割:不要な光を遮る
レンズフードは、光をコントロールするための最も原始的で、
そして最も確実な手段です。
強い光がレンズに直接入ると、
内部で反射が起こり、フレアやゴーストが発生します。
結果として、写真全体が白っぽく霞んだように見えたり、
コントラストが落ちたりしてしまいます。
フードはこの“余分な光”を物理的に防ぐことで、
画質と階調を守る働きをします。
特に逆光や炎天下では、フードの有無で仕上がりがまるで違います。
フレア・ゴーストを防ぐための構え方
たとえば太陽が画面の端にある場合、
わずかな位置のズレで光がレンズ面に反射します。
このとき有効なのが、**「フード+構図+身体の影」**の三段構えです。
撮影者自身が太陽の影に入り込むように立ち位置を変えると、
レンズに入る光がやわらぎ、コントラストが戻ってきます。
また、片手や帽子をレンズ上部にかざして“影をつくる”方法も有効です。
これは「人間フード」と呼ばれるほど、
プロも現場で多用するテクニックです。
炎天下でのフード運用:熱と反射の両対策
太陽光が直接レンズ前面に当たると、
レンズ内の空気が熱で揺らぎ、陽炎(かげろう)状のゆらめきが生じることがあります。
また、地面や白い壁からの反射光が、
下方向からレンズに入り込むケースもあります。
このときは、少し下向きにカメラを構えるか、
アングルを数度ずらすだけで大きく改善します。
地面の照り返しが強い場合、
黒い布やタオルを下に敷くだけでも反射を減らせます。
フードの種類と使い分け
・花形フード(バヨネット式):広角〜標準レンズ向け。
画角を邪魔せずに遮光しやすい。
・円筒型フード:望遠レンズ向け。
直射光をしっかり防げる。
逆光撮影が多い場合は、円筒型の方が効果的です。
ただし、広角レンズに長いフードを使うと画面の四隅がケラレる(暗くなる)ため、
焦点距離に合った純正フードを使うのが基本です。
フードと露出補正の“二段構え”で安定させる
フードは「光の入り方そのものの制御」。
この二つを組み合わせることで、
カメラが迷わず、露出のブレも減ります。
たとえば逆光で被写体の顔が暗いとき、
まずフードで余計な反射を遮り、
その上で+0.3〜+0.7段ほど補正する。
すると、背景の光がやわらぎ、顔の階調も自然に残せます。
物理的な遮光を整えたうえで、
数値的に微調整する――この順序が最も安定します。
✅ まとめ
・フードは「余分な光を物理的に防ぐ」ための最重要装備。
・逆光では構図と立ち位置もセットで考える。
・炎天下では熱や反射も敵になる。小さな角度調整が効果的。
・花形/円筒フードは焦点距離に合わせて使い分ける。
・「フード→補正」の順で調整すると、失敗が少ない。
撮影シーン別:逆光・炎天下での具体策
屋外ポートレート:顔を明るく、背景を飛ばさない
真夏の午後、人物の背後に太陽があると、顔が影になりがちです。
まず、測光モードをスポットまたは中央重点に変更し、顔の明るさを優先します。
初期補正は+0.3〜+1.0段が目安です。
背景の空が飛びすぎる場合は、−0.3段まで戻してバランスを取りましょう。
レンズフードを装着し、太陽が直接レンズに入らないよう、
被写体の角度をわずかに調整します。
さらに、白レフ板や小型フラッシュ(日中シンクロ)を使えば、
顔の影がやわらぎ、自然な立体感が生まれます。
背景のハイライトを少し抑え、顔の明るさを“主役”にする意識が大切です。
風景撮影:光芒と白飛びをコントロールする
太陽を画面に入れて撮る風景写真では、マイナス補正が基本です。
太陽の光をそのまま記録すると白飛びしやすいため、−0.3〜−1.0段を目安に調整します。
絞りをF11〜F18程度まで絞ると、光が放射状に広がる“光芒”をきれいに表現できます。
ただし、絞りすぎると回折(シャープさの低下)が起きるため、
F16前後で止めるのが安全です。
また、炎天下の強光下ではNDフィルターを併用することで、
露出を落としながら光芒を維持できます。
構図を決めたら、ヒストグラムで右端の飛びを確認し、
白飛びをギリギリ防ぐ設定を探るのがコツです。
植物・花・透過素材:光を“味方”にする
この場合、+0.3〜+0.7段のプラス補正で暗部を明るくすると、
透過した色の深みがきれいに出ます。
ただし、光が強すぎると花びらが白く飛んでしまうため、
露出補正と構図を何度か調整して“ちょうどよい透け具合”を探します。
フードは必ず装着し、太陽が画角に入らないように角度を微調整します。
背景が明るい場合は、開放寄り(F2.8〜F4)にしてぼかすと、
被写体が浮かび上がるように見えます。
逆光の柔らかさを活かしながら、被写体の色を引き出すことがポイントです。
炎天下のスポーツ・動体撮影:スピードと光の両立
炎天下のグラウンドでは、反射光が強く、被写体が白く飛びやすくなります。
まず、シャッタースピードを1/1000秒以上に固定し、
ISOは100〜400に抑えます。
マイナス補正(−0.3〜−0.7段)をベースにして、
被写体のユニフォームや肌の階調が飛ばないようにします。
照り返しが強いときはND8〜ND16を使用し、
露出を下げつつ動きを止めるバランスをとります。
フードは必須で、
観客席など白い反射面を避ける立ち位置を選ぶと、
コントラストが安定します。
撮影後はヒストグラムで白飛びを確認し、必要に応じて−補正を少し強めましょう。
✅ まとめ
・ポートレートでは“顔優先”で+補正、フードとレフで自然な明るさを。
・風景は−補正+絞りで光芒を狙い、NDフィルターで白飛び防止。
・花や葉の透過光は+補正で色を引き出す。
・スポーツはシャッター優先+軽い−補正で動きと光を両立。
・どのシーンでも、露出補正とフードを「セットで考える」ことが安定の鍵。
| シーン | 目的 | 推奨設定・操作ポイント | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 屋外ポートレート | 顔を明るく写し、背景を飛ばさず自然な立体感を出す。 | ・測光モード:スポットまたは中央重点。 ・露出補正:+0.3〜+1.0段。 ・レンズフード装着、太陽がレンズに入らない位置に立つ。 ・白レフ板または日中シンクロで影を補う。 | 背景の空が飛びやすい。 補正を強くしすぎないようヒストグラム確認。 |
| 風景(太陽を入れる構図) | 光芒やドラマチックな逆光表現を狙いながら白飛びを防ぐ。 | ・露出補正:−0.3〜−1.0段。 ・絞り:F11〜F18(光芒効果)。 ・NDフィルター併用で露出を下げる。 ・ヒストグラム右端をチェック。 | 絞りすぎ(F22以上)は回折に注意。 強光下ではNDで調整。 |
| 植物・花・透過素材 | 光を透かして色の深みや柔らかさを出す。 | ・露出補正:+0.3〜+0.7段。 ・開放寄り(F2.8〜F4)で背景をぼかす。 ・フードを装着し、太陽が画角外になるよう構図調整。 | 光が強すぎると花びらが白飛び。 数回撮って適正露出を探る。 |
| 炎天下のスポーツ・動体撮影 | 強光下で白飛びを防ぎつつ、動きを止める。 | ・シャッタースピード:1/1000秒以上。 ・ISO:100〜400。 ・露出補正:−0.3〜−0.7段。 ・ND8〜ND16使用で露出抑制。 ・フードを常用し、反射面を避ける立ち位置を選ぶ。 | 照り返しが強いとハイライトが飛びやすい。 ヒストグラム確認で調整。 |
| 夕方〜低光量の逆光ポートレート | 柔らかい光で温かみを出す。 | ・露出補正:+0.3〜+0.7段。 ・ホワイトバランスを「太陽光」または「日陰」設定。 ・背景の光をぼかして逆光の縁取りを演出。 | 補正しすぎると全体が淡くなりやすい。 コントラストを意識。 |
注意すべき落とし穴と対策
露出補正の“やりすぎ”が招く不自然さ
+や−を大きく振りすぎると、
明るさのバランスが崩れ、写真全体が“作り物のよう”に見えることがあります。
たとえば+1.3段を超える補正では、
被写体の肌が白く飛び、背景が溶けたように写ることもあります。
逆に−1.0段を超える補正では、
影が黒く潰れ、細部の質感が失われます。
対策はシンプルです。
0.3段ごとに段階調整し、撮影→確認→再補正のループを作ること。
これはプロでも徹底しています。
感覚ではなく、ヒストグラムの“端”を見る習慣が身につくと、
補正の精度が一気に上がります。
フードを過信すると、逆効果になることも
広角レンズで長いフードを使うと、
四隅がケラレて暗くなることがあります。
また、逆光で太陽をわざと入れたい構図では、
フードが光を遮りすぎて“味”が消えることもあります。
そんなときは、一部を少し外す・短いフードに変えるという柔軟さが必要です。
特に夕方の低い太陽光では、
フードの角度よりも“撮影者の立ち位置”の方が効果的に光をコントロールできます。
強光・高温による機材トラブル
センサーの温度が上がると、
ノイズが増えたり、長時間露光で色かぶりが発生することもあります。
特に金属外装のカメラは、
直射日光下で急速に温度が上昇し、シャッター速度が不安定になることもあります。
対策として、
・撮影の合間にカメラをタオルで覆う
・直射下に置きっぱなしにしない
・バッグに戻す際はファスナーを全開にして通気を確保
といった“機材の熱休憩”を取り入れてください。
夏の屋外撮影では、撮影者よりも先にカメラがバテます。
RAW現像への“過信”も禁物
確かにRAWには補正余地がありますが、
白飛びや黒つぶれを完全に戻すことはできません。
特に炎天下の白い被写体(服・壁・砂浜)は、
撮影時に飛んでしまうと情報自体が残っていません。
RAW現像は“微調整の延長線”であり、
撮影時に露出を外さないことが前提です。
「RAWで救える」は、正確な露出の上に成り立つ保険だと考えてください。
最後に:露出は“数値”よりも“意図”
露出補正やフード、NDフィルターは、
すべて「どう撮りたいか」という意図に従って使う道具です。
単に明るくする・暗くするではなく、
「何を見せたいか」「どんな光を残したいか」を最初に決めてから操作する。
その順番が逆になると、
どんなに正しい数値でも“味気ない写真”になります。
だからこそ、現場では一度カメラを下ろして、
目の前の光を“肉眼で観察する時間”を持つことが大切です。
✅ まとめ
・露出補正は小刻みに調整する。0.3段ずつが理想。
・フードは万能ではない。構図と立ち位置も合わせて調整。
・炎天下では機材が熱を持つ。休ませながら撮る。
・RAW現像は保険。撮影時に正確な露出を取ることが第一。
・「どう撮りたいか」という意図がすべての起点。
さいごに
逆光や炎天下というのは、誰にとっても難しいテーマです。
露出補正をかけても思った通りにいかないことが多く、
画面を見て「また暗い」「また白い」とため息をつく日もあります。
けれど、その繰り返しこそが「光を読む目」を育ててくれます。
露出は、カメラの数値ではなく意図を形にする言語です。
+0.3段の明るさの裏には、「もう少し顔を見せたい」という気持ちがあり、
−0.3段の暗さの裏には、「眩しさを残したい」という判断があります。
レンズフードは、ただの影を作る道具ではありません。
光を“整える手”です。
そこにNDフィルターや測光モードの切り替えを重ねることで、
あなたの写真は“太陽の下で自由に描ける”ようになります。
私自身も、何度も失敗しました。
顔が真っ黒になったり、背景が真っ白になったり。
でも、あの瞬間を繰り返してきたからこそ、今は太陽を怖がらなくなりました。
次に晴れた日が来たら、ぜひカメラを持って外に出てください。
太陽を避けるのではなく、味方につけるつもりで。
光の向こうに立つ一歩が、写真を変える第一歩です。
✅ まとめ
・露出補正とフードは、光を“操る”ための基礎。
・逆光は敵ではなく、表現のチャンス。
・失敗は判断の蓄積。繰り返すほど光を読めるようになる。
・太陽を怖がらず、“意図”を持って撮ることが上達の近道。
初めてカメラを選ぶ段階の人へ
「2025年版|子どもの行事に初カメラデビュー。失敗しないミラーレス選びの考え方」
カメラ選びの基準を、用途別に整理しました。


参照情報(出典整理)
- Canon公式:レンズアクセサリー・フード一覧
- Canon公式:レンズアクセサリー(フィルター・レンズフード等)
- Nikon公式:ARCREST ND8フィルター 製品情報
- Nikon公式:NDフィルターの使いかた(フォトテック・レンズ講座)
- Tamron公式:ダイナミックレンジとは何か(Impression特集)
- Sony公式:露出補正・測光モードの基本ガイド
- FUJIFILM公式:Xシリーズ 露出補正と測光設定ガイド
- OM SYSTEM公式:露出補正とヒストグラムの見方
- カメラのキタムラ公式:NDフィルター・PLフィルターの基礎知識
- ヨドバシカメラ公式ガイド:レンズフードの種類と役割
本記事の内容は、各メーカー公式サイトおよび取扱説明書など一次情報を基に一般的な撮影知識としてまとめたものです。
記載された設定値・効果・使用方法は、撮影環境・機種・ファームウェアのバージョン等により異なる場合があります。露出補正やNDフィルターの操作値は参考例であり、読者の機材・状況に応じて適切に調整してください。
本記事を利用した撮影結果や機材トラブル等について、筆者および本サイトは一切の責任を負いません。また、掲載しているURL・仕様・設定内容は執筆時点の公式情報を参照していますが、
最新の情報は各メーカー公式ページにてご確認ください。